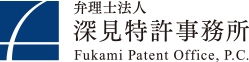契約終了後の特許発明の実施を禁止する条項は、特許無効が確定する時まで失効しないとした、特許法院および大法院判決
1.概要
複合シート製品を生産および販売する、特許権者である株式会社A(以下「A社」)と、A社と同種業を営む株式会社E(以下「E社」)とは、特許の実施契約を含む相互協力契約を締結しており、当該契約には、契約終了後にA社の特許発明をE社が実施することを禁止する実施禁止義務条項が含まれていました。
A社は、契約終了後にE社が無断でA社の特許発明を実施しているとして、相互協力契約違反に基づく損害賠償を請求する訴訟を提起しました。これに対して株式会社Eは、当該特許は無効であり、上記契約は効力を喪失しており、E社が実施した具体的な形態は自由実施技術であることから、上記契約には違反してはいないと主張しました。
このような当事者の主張に対して特許法院および大法院は、いずれも、特許無効が確定したとしても実施禁止条項は無効が確定する時までは失効されずに有効に存続し、株式会社Eは実施禁止義務に違反したものと判断しました(特許法院判決2024.6.27言渡し2022ナ1975、大法院判決2024.11.20言渡し2024ダ270105)。
2.事件の経緯
(1)相互協力契約の締結および契約の終了
A社は、液晶テレビ用バックライトの複合シートに関する特許(以下「本件特許」)の特許権者です。A社とE社は2009年2月27日、複合シート製品の共同生産・販売を目的として相互協力契約を締結しました。当該相互協力契約の第6条第2項および第3項には、以下の『』内のように規定されています。
『第2項:E社は契約が満了するか又は中途合意解約がなされても、A社から習得した複合シート特許技術を許諾なく独自に使用し又は他人が使用するように伝えることはできず、その他の特許権を侵害する一切の行為をしてはならず、これに違反したときには損害を賠償しなければならない。
第3項:E社は契約期間、および、契約期間満了又はその他の解約等の理由が発生した後でも類似製品を生産してはならず、これに違反したときには損害を賠償しなければならない。』
E社は2013年8月8日頃、A社に対し、A社の追加意見がない場合には相互協力契約の延長をしない予定である旨の通知をした後、A社とE社との間で契約期間延長に関する合意は成立せず、当該相互協力契約は、契約締結から5年後の2014年2月27日に期間満了で終了しました。その後E社は、関連製品の独自生産および販売を進めました。
(2)特許無効審判の請求
E社は2014年2月27日、A社等を相手取り、特許審判院に本件特許に係る無効審判を請求し、それに伴う審判および訴訟手続きを経て本件特許は進歩性が否定され、2017年6月9日に特許無効が確定しました。
(3)相互協力契約違反に基づく損害賠償を求める訴訟の提起
A社はE社に対し、相互協力契約違反に基づく損害賠償を求めて、ソウル中央地方裁判所(以下「地裁」)に訴訟を提起しました。当該訴訟において地裁は2022年8月19日に、A社の主張の一部を認めて、B社に損害賠償を命じる判決を下しました。それに対して、A社およびE社の双方が特許法院に上訴しました。
3.特許法院における審理
(1)当事者の主張
特許法院への上訴に際してA社は、A社はE社が当該契約満了後も特許技術を無断で使用し類似製品を生産・販売して損害を被ったと主張しましたが、特許法院での審理に際して、A社は地裁での勝訴部分を超える損害賠償請求権を放棄しました。
E社は、本件特許は無効であることから上記契約は効力を喪失しており、また、E社が実施した具体的な形態は自由実施技術であることから、上記契約には違反してはいないと主張しました。
(2)特許法院の判断
上記当事者の主張に対して特許法院は、A社の主張を認めて、以下のように判断しました。
①相互協力契約の有効性および終了後の効力
本件特許が無効にされたことにより契約の効力が消滅したというE社の主張に対して、特許法院は、契約締結当時において当該契約は特許の有効性を保証しておらず、たとえ2017年6月9日に本件特許の無効が確定したとしても、本件相互協力契約で定めた特許発明実施禁止条項は少なくとも本件特許の無効が確定した2017年6月9日までは有効であると認めるのが妥当であると判断しました。さらに、契約の生産禁止義務についても、特許が有効か否かとは関係なく効力を維持するとして、E社の主張を斥けました。
したがって特許法院は、2014年2月27日に契約が満了した後も、2017年6月9日の特許無効確定の前までは、契約の実施禁止義務および生産禁止義務は有効であると認定しました。
②特許無効と契約との関連性について
本件特許の有効性と契約の効力との関係について、特許法院は、大法院判決2018ダ287362(2019年4月25日言い渡し)等を参照して、「特許発明実施契約が締結された後に契約の対象である特許権が無効と確定した場合特許発明実施契約が契約締結時から無効となるかは、特許権の効力とは別と判断しなければならないのと同じように、相互協力契約が特許権の通常実施権などを想定しているとしても、相互協力契約の無効または失効の有無と争点特許権の効力は別に判断しなければならない」との判断を示しました。
③自由実施技術の抗弁について
E社が生産した製品が自由実施技術による製品に該当するとしても、それに基づくE社の主張は、本件相互協力契約違反によるA社の損害賠償請求を阻止するための有効な抗弁とは認められないと判断しました。
④特許権侵害および損害賠償責任について
A社が、特許の訂正請求前の請求項を基準として、E社が契約終了後に類似製品を生産・販売して特許を侵害したと主張したのに対し、E社は、特許無効審判での訂正請求後の請求項を基準として非侵害を主張しました。それに対して特許法院は、本件特許の請求項を確定するのは当事者の意志あるいは解釈により決定される問題であることを鑑みると、特許の訂正請求前の請求項を基準として構成比較をすることが妥当だと判断し、E社製品が訂正前の請求項を基準として本件特許発明を実施したと認定し、これによる損害賠償責任があるものと判断しました。
⑤損害賠償算定方式について
特許法院は、契約に定められた損害額算定方法に従い、不正競争防止法に基づいてE社の利益をA社の損害額と推定するものと判断しました。
⑥類似製品生産の有無について
特許法院は、E社の製品が本件特許発明と構造および作用効果が類似していることから、市場代替の可能性があると認定し、E社は契約に違反すると判断しました。
(3)特許法院の判決と、E社による大法院への上訴
上述の判断に基づいて特許法院は、第一審である地裁の裁判でのA社の勝訴部分について、E社に対する相互協力契約違反に基づく損害賠償請求を認める判決を下しました。
それに対してE社は、大法院に上訴しました。
4.大法院の判断
大法院への上訴に際してE社は、特許法院での審理における主張に基づいて、上述の特許法院の判断を否定する上訴理由を示しました。それに対して大法院は、E社の上訴理由をすべて棄却し、特許法院の判断に全面的に同意して、A社のE社に対する損害賠償請求を認める判決を下しました。
当該判決において大法院は、過去の大法院判決を引用して、次の点について明確に指摘しています。
『特許権者と相手方との間で特許権者の許可なく特許発明の実施を禁止する契約(以下「特許発明禁止契約」という)が成立し、特許が無効とされたとしても、契約締結時から特許発明実施禁止契約が履行不能な状態にあったとは言えず、特許の無効が確定した時点から特許発明禁止契約が効力を失うことになったと言えるだけである(大法院2014.11.13.言渡し、2012ダ42666、42673判決など)。
したがって、契約自体の無効性について別途理由がない限り、特許権者は、原則として、上記契約に基づく特許発明の実施禁止義務が効力を有する期間に、特許発明を実施した相手方に対して債務不履行損害賠償を請求することができる(大法院2019.4.25.言渡し、2018ダ287362判決など)。この場合、相手方が特許発明を実施した具体的な形態が、既知の技術から技術分野について普通の知識を有する者が容易に実施することができる、いわゆる自由実施技術に該当するとしても、その事情だけでは、特許権者と特許権者との合意により特許発明の実施を禁止する契約の拘束力を免れることはできない。』
5.実務上の留意点
本件判決を踏まえ、特許の実施契約を含む相互協力契約の当事者や、そのような契約に関与する実務者は、特に「契約の効力の独立性」に関連して、以下の点に留意することが望まれます。
(1)特許権者は、製品の生産および販売のために協力会社と契約を締結し特許発明の実施を許諾する場合、当該契約には、契約終了後の特許発明実施禁止条項を定めることがあります。契約の対象となる特許が無効と判断された場合、そのような契約の有効性の判断は、契約の解釈に基づいてなされるのであって、特許の無効確定により自動的に当該契約の効力が喪失するものではないことを考慮し、状況に応じて、契約内容を十分理解し、契約内容が具体的事実関係にどのように反映されるかを詳細に分析して対処する必要があります。
(2)具体的には、特許発明の実施に際しての契約に明示された義務については、当該特許が無効にされた場合にも、特許権侵害の場合とは異なり、契約の効力の独立性に基づいて有効であり、契約上の義務を果たす責任がある場合があることに留意すべきです。
(3)また、生産した製品が、当業者にとって公知技術から容易に導き出すことが技術的に可能であったとしても、そのことをもって契約上の義務は回避できない場合があること、すなわち、自由技術の抗弁には限界があることを認識する必要があります。
[情報元]
1.KIM & CHANG IP Newsletter | 2025 Issue1 | Japanese「大法院、契約終了後に特許発明の実施を禁止する条項は、特許無効が確定する時まで失効せず、特許発明の実施は契約に違反すると判断」2025.2.18
https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=31293
2.本件特許法院判決2024.6.27言渡し2022ナ1975(韓国語原文)
https://patentschool.co.kr/data/file/lms_board/3542488369_o8XbKLYN_cb85530a6d8a9938ad63d4e6121c351c14eca98f.pdf
3.本件大法院判決2024.11.20言渡し2024ダ270105(韓国語原文)
https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2024%EB%8B%A4270105