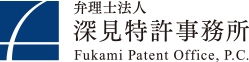時期に遅れて提出された主張の取り扱いに関するUPC第一審判決紹介
Ⅰ.事件の背景
統一特許裁判所(UPC)での訴訟手続は非常に迅速に進み、最終の口頭審理は出訴から1年以内に行われます。このようにUPCにおける訴訟手続の迅速さは、米国におけるほとんどの特許侵害訴訟とは非常に異なるものです。
UPCでは、主張の陳述、抗弁の陳述、答弁書、答弁書に対する反論など、主張や証拠を提起するためのいくつもの機会を当事者のために用意していますが、UPCの厳しい時期的制限に適合するために、UPCは通常、当事者が訴訟のできるだけ早い段階でその主張を提出することによって訴訟を「前倒し」に進めることを要求しています[i]。
UPCの前倒しの性質と、当事者が主張を提出するさまざまな機会とのバランスをとるために、UPCは、時期に遅れて提出された主張のうち、採用されないリスクがあるものの種類を明確にしつつあります。特に、以下に紹介する最近の2つのUPCの第一審判決から、いくつかの重要な点が明らかになりつつあります。
Ⅱ.UPC中央部の判決:遅れて提出された特許取消の主張のリスク
(事件情報:Tandem Diabetes Care, Inc. v. Roche Diabetes Care GmbH(UPC-CFI-454/2023))
1.事件の経緯
(1)訴訟の提起
Tandem Diabetes Care, Inc.(以下、「Tandem社」)は、特許権者であるRoche Diabetes Care GmbH(以下、「Roche社」)に対してUPC中央部のパリ支部(以下、単に「中央部」と称する)に取消訴訟を提起しました。
(2)被告の抗弁と侵害訴訟の提起
Tandem社による取消請求に対して、Roche社は取消請求に対する抗弁を提出して特許クレームを訂正するための20数個の補助請求を提出するとともに、本件取消訴訟で争点となっている独立クレームに加えて他の従属クレームについてもTandem社による侵害を主張して特許侵害訴訟を別途UPCのハンブルク地方部に提起しました[ii]。
(3)原告の対応
Tandem社は、取消訴訟におけるRoche社の抗弁に対して新しい先行技術文献を提示するとともに、ハンブルグ地方部での並行侵害訴訟で主張された従属クレームにも無効理由を申し立てることで、無効の主張を拡大しようとしました。
(4)被告の対応
Roche社は、Tandem社による拡大された無効の主張による追加攻撃を許容することに反対するとともに、特許クレームを訂正するためのさらなる補助請求を行いました。
(5)中央部の判決
中央部は、2024年12月18日付の判決において、遅れて提出された複数の主張について以下のように対処しました。
2.中央部の判断
報告担当裁判官(judge-rapporteur)は、中間会議[iii]で、独立クレームおよび従属クレームの双方に関連するTandem社の新たに提出された先行技術と無効の主張を排除するとともに、Roche社が特許をさらに訂正することを認めませんでした。当事者は、裁判官合議体[iv]に対して、口頭審理において報告担当裁判官によるこれらの決定を再検討するよう要請しました。合議体は、報告担当裁判官に同意する判決を下しました。合議体の判決の内容を整理すると以下の通りです。
(1)提出時期に関する原則について
合議体の判決は、取消訴訟においては原告が可能な限り早い機会に完全な主張をすること、すなわち、無効理由を詳細に特定するとともに新規性または進歩性の欠如の主張を裏付けるために依拠した先行技術文献を特定した主張をしなければならないことを再度強調しました。
UPCによれば、原告の理由および書面は、係争の主題を定義し、被告が自分に対してなされた申立てを理解して適切な抗弁を準備できるようにするとともに、裁判所が訴えに関する裁判管轄権の範囲を決定できるようにするものです。したがって、特許の取消を求める原告は後になって、最初の取消の陳述において提出されなかった文献に基づいて、または被告が補助請求によって訂正した特許クレームに関連しない新しい文献に基づいて、新しい主張を提出することはできません。被告の補助請求に応じて原告が提出した主張または文献は、もしもそれが当初の訴えに対して提出できたはずのものであったり、訂正に具体的に対応していない場合には、そのような主張または文献の提出は禁止される可能性があります。
(2)取消訴訟において遅れた提出が許容される可能性がある場合
後から提出された主張を許容できるかは各事件の具体的な状況に依存します。UPCは、訴訟を前倒しに進めるという厳格な基準に従うことが当事者および裁判所にとって度を超えた厳しさのものとなるような場合に取り得る例外的なシナリオがあり得ると指摘しました。遅れた提出が認められる例外的なシナリオとして、取消訴訟の原告は、取消しに対する抗弁における被告の申立てを予期できなかったであろう場合には、新しい事実で応答することがあり得ます。当事者は、手続き期間中に文献が入手可能になり、かつ当事者が最初から最後まで熱心に行動した場合には、手続き期間の後の段階で文献を提出することが許容される可能性があります。
(3)中央部による本件の結論
本件はこれらの例外的なシナリオのいずれにも当てはまらないため、合議体は報告担当裁判官の決定を再確認し、Tandem社は新たな先行技術文献を用いた追加の無効の主張を提起することも、新たに従属クレームに異議を申し立てることもできないと判断しました。合議体はまた、Tandem社の追加の無効の主張が容認されなかったことから、Roche社による特許のさらなる訂正も不要であるとして、訂正の却下も支持しました。合議体は、新たに提出された先行技術は、訂正された特許および取り消しに対する抗弁の申し立てに対応するという特定の目的のためにのみ容認されることを強調しました。
Ⅲ.UPC北欧バルト地方部の判決:遅れて提出された主張に対する微妙なアプローチ
(事件情報:Edwards Lifesciences Corp. v. Meril Life Sciences Pvt Ltd. et. Al.(UPC-CFI-380/2023))
1.事件の経緯
(1)訴訟の提起
Edwards Lifesciences Corp.(以下、「Edwards社」)は、Meril Life Sciences Pvt Ltd. et. Al.(以下、「Meril社」)による特許侵害を主張してUPCの北欧バルト地方部に侵害訴訟を提起しました。訴えの中でEdwards社は、文言侵害が成立しない場合における均等侵害の成立について一般的な表現で示唆していましたが、具体的な内容は必要に応じて後日提示するとの記述に止まっておりました。
(2)被告の抗弁および反訴
この侵害訴訟に対して、Meril社は、2つの無効理由に基づいて進歩性の欠如を主張する取消しの反訴を北欧バルト地方部に提出しました。
(3)原告の対応
取消反訴に対してEdwards社は特許の訂正請求を提出しました。また、Edwards社は文言侵害が成立しない場合の均等侵害の成立について具体的な主張を行いました。
(4)被告の対応
Meril社は、Edwards社による訂正請求に対して追加の無効理由を提出し、この新しい申立ては、共通の一般常識に関するEdwards社の反論に対する回答であると主張しました。また、Meril社は、Edwards社による均等侵害の主張は時期に遅れた主張であるので却下されるべきであると主張しました。Meril社はさらに、被疑侵害品は本件特許の一部のクレームについてその特定の構成要素を欠いているという新たな非侵害の主張を行いました。
(5)北欧バルト地方部の判決
2024年12月10日、本件訴訟において北欧バルト地域部は、中間会議後に下された判決で、当事者の間で遅れて提出されたいくつかの主張を容認するか否かについて対処しました。
2.北欧バルト地方部の判断
(1)遅れて提出された無効理由
前述のUPC中央部の判決と同様に、北欧バルト地域部は、Edwards社による訂正請求に対応するためにMeril社によって遅れて提出された有効性に対する異議申し立ての理由を不適格として却下しました。UPC北欧バルト地方部は、進歩性を攻撃する追加の理由は除外されるべきであるというEdwards社の意見に同意しました。その理由は、取消に対する最初の陳述に含めることができたはずの取消理由は、相手方が提起した抗弁の内容または特許の訂正の請求に関連せず、したがってそれらに対する正当な応答を構成しない場合は容認されないからであります[v]。
(2)遅れて提出された反論
遅れて提出された無効理由の却下とは対照的に、UPC北欧バルト地方部は、共通一般知識に関する文書の遅れた提出を認めました。Meril社は、取消を求める当初の反訴において、共通一般知識に関する具体的な陳述を含めました。Edwards社はこれらの陳述に異議を唱え、Meril社はそれに応じて新しい文書を提出しました。UPC北欧バルト地方部は、Meril社が共通一般知識の範囲を示すために文書を使用することは禁じられていないと判断し、文書および裏付けとなる論拠が、Meril社が反訴で以前に行った具体的な陳述に関連していることを強調しました。したがって、新しい文書の導入は、既存の理由と主張を証明するのに役立つものであり、そしてEdwards社による反論に対応するものであることから、受理可能になりました。
(3)遅れて提出された侵害申し立て
北欧・バルト海地域部は、訴えの陳述における侵害の主張に必要な具体性の程度についても取り上げました。均等論に基づく侵害については、Edwards社は、訴えの陳述において単純明快な主張のみを行いました。むしろ、Edwards社はMeril社の応答を待って均等論の詳細を提供するつもりでした。Edwards社が後に均等論に関する議論を具体化させたとき、Meril社は、その議論が時を逸しており必要な内容が不足しているため、UPC北欧バルト地方部にその議論を受理できないとして却下するよう求めました。
Meril社の要求に対応して、UPC北欧バルト地方部は、UPCの手続きは前倒しであるものの、請求人は、その後追加する機会なしに訴えの陳述において考えられるすべての議論を提出することまでは期待されていないと指摘しました。したがって、当事者は、自らの主張を裏付ける機会を持つことができます。さらに、訴えの陳述内容について詳細に規定するUPC手続規則の規則13には、その後の請求を禁止するような条項は含まれていません。代わりに、UPCは、請求が以前に提起されなかった理由と、被告が応答する合理的な機会があるかどうかを検討する必要があります[vi]。
UPC控訴裁判所はまた、均等論の主張は、UPC手続規則の規則263[vii]および規則13で定義されている事件に対する修正ではないと述べています。均等論の主張は、被疑侵害品と本件特許とが同一であることを主張しています。したがって、侵害に関する新たな主張によって範囲が変わることはなく、事件の修正も必要ありません。ここで、UPC北欧バルト地方部は、訴訟手続きの開始時点では、どの特許要素が争われ、均等の議論を必要とするか、を予測することは困難であるという点でEdwards社に同意しました。したがって、UPC北欧バルト地方部は、Edwards社によるその後の均等の議論は許容されると結論付けました。
(4)遅れて提出された非侵害の主張
最後に、特許訂正請求に対する反論および回答において、Meril社は非侵害の新たな主張を追加しました。UPC北欧バルト地方部は、新たな主張は容認できないと主張したEdwards社に同意しませんでした。Meril社は、訂正された特許クレームによりクレーム解釈に関する新たな立場を発見し、その結果非侵害を発見したと主張し、UPC北欧バルト地方部もこれに同意しました。したがって、Meril社は最初の機会に主張を提出しており、訴訟の前倒しの性質に違反しませんでした。したがって、UPC北欧バルト地方部は、UPC手続規則の前文を考慮して解釈された規則13は、Meril社の主張を適時に限定的に彼らの立場を修正したものとして認め、容認できると判断しました。
Ⅳ.時期に遅れて提出された主張の取り扱いの要点
上記のUPC第一審判決から明らかになった事項の留意点を整理すると以下の通りです。
1.取消訴訟の場合
今回のUPC中央部判決によって確認されたように、特許取消の申立てを行う被疑侵害者は、最初の申立てにおいて、申立ての対象となっているすべてのクレームに対応付けられたすべての先行技術を含む、すべての無効理由を提示する必要があります。
対照的に、共通一般知識の証拠などは手続き期間内のうちの後の段階で提示することができます。
2.侵害訴訟の場合
侵害訴訟を提起する場合、原則として特許権者は、侵害であると主張する被告製品のいずれについても、主張可能なすべての特許クレームを列挙して権利主張する必要があります。
しかしながら今回のUPC北欧バルト地方部判決により、特許権者は、被告の抗弁に応じて、手続き期間内のうちの後の段階で、特許を訂正するための補助請求を提出したり、均等論による侵害などの追加の侵害理論を主張したりできることが確認されました。訂正後の特許クレームに対する抗弁において、被告は、訂正後の特許クレームに対する非侵害の新たな主張を提示することができます。
3.その他の留意点
これらのこれらUPC第一審判決例の展開とは別に、UPCの当事者は、その事件を扱う第一審裁判所の先行する判決に特に注意を払う必要があります。今回のUPC第一審判決に先行するUPCの控訴裁判所の判決[viii]が明らかにしているように、これらの第一審裁判所には「一定の裁量権」があり、控訴裁判所が第一審裁判所の判決を審査する権限は制限されます。
以上のことから、UPCでの訴訟の当事者となった場合には、管轄の裁判所の過去の判断についてよく確認しておく必要があるものと思われます。
[情報元]
1.Legal Lens on the Unified Patent Court |Q1 2025
“RISK OF INADMISSIBLE, LATE-FILED ARGUMENTS”
(https://www.mwe.com/pdf/legal-lens-on-the-unified-patent-court-q1-2025/)
2.DECISION of the Court of First Instance of the Unified Patent Court Central division (Paris seat)
issued on 18 December 2024 in the revocation action No. ACT_589997/2023 UPC_CFI_454/2023(UPC中央部パリ支部判決原文)
(https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/files/api_order/2024-12-18%20CD%20Paris%20%20UPC_CFI_454-2023%20%20ORD_598508-2023%20%20Act_589997-2023%20anonymized.pdf)
3.UPC_CFI_380/2023 Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court delivered on 10 December 2024(UPC北欧バルト地方部判決原文)
(https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/files/api_order/E57E077591EDFB8F671CD359B02A1419_en.pdf)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊
[i] UPC協定の手続規則の前文、第7段落は以下のように規定しています。
“7. In accordance with these principles, proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within one year whilst recognising that complex actions may require more time and procedural steps and simple actions less time and fewer procedural steps. Decisions on costs and/or damages may take place at the same time or as soon as practicable thereafter. Case management shall be organised in accordance with these objectives. Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings.”
[ii] UPCは侵害訴訟および取消訴訟の双方に管轄権を持っていますが、UPCでは中央部および地方部/地域部の裁判所が取消訴訟および侵害訴訟を並行して審理する分岐訴訟が発生することがあります。
[iii] 「報告担当裁判官(judge-rapporteur)」および「中間会議(interim conference)」はUPC特有の制度であり、詳細についてはUPC公式HPの“Frequently Asked Questions-Interim procedure”(下記のURL)をご参照ください。
https://www.unified-patent-court.org/en/faq/interim-procedure#faqs
[iv] 合議体は、裁判長を兼任する報告担当裁判官、法律資格のある裁判官、および技術資格のある裁判官で構成されていました。
[v] Bitzer Electronics A/S v. Carrier Corp., UPC_CFI_263/2023, ACT_555899/2023 (Central Division Paris July 29, 2024)
[vi] OrthoApnea S.L. and Vivisol B BV v. ***、UPC_COA_456/2024, APL_44633/2024(2024年11月21日)を参照。
[vii] UPC協定の手続規則の前文、第7段落は以下のように規定しています。
Rule 263 – Leave to change claim or amend case
- A party may at any stage of the proceedings apply to the Court for leave to change its claim or to amend its case, including adding a counterclaim. Any such application shall explain why such change or amendment was not included in the original pleading.
- Subject to paragraph 3, leave shall not be granted if, all circumstances considered, the party seeking the amendment cannot satisfy the Court that:
(a) the amendment in question could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage; and
(b) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of its action.
- Leave to limit a claim in an action unconditionally shall always be granted.
- The Court may re-consider fees already paid in the light of an amendment.
[viii] OrthoApnea S.L. and Vivisol B BV v. ***、UPC_COA_456/2024, APL_44633/2024(2024年11月21日)を参照