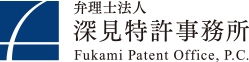国内裁判所の国境を越えた裁判管轄権およびUPCのロングアーム管轄権を認めたCJEU判決紹介
1.事件の概要
欧州連合司法裁判所(the Court of Justice of the European Union:CJEU)は、EU加盟国の国内裁判所および統一特許裁判所(the Unified Patent Court:UPC)の機能を大幅に拡大し、これらの裁判所が、国境を越えた差し止め命令を発行し、かつそれぞれの裁判所の管轄外の国における特許侵害行為を裁くことができるようにする判決を下しました(2025年2月25日CJEU大法廷判決番号Case C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB事件:以下、「本件判決」)。
本件判決によれば、被告の居住国であるEU加盟国の裁判所において、当該EU加盟国以外のEU加盟国およびEU非加盟の第三国における侵害についても包括的に特許を執行することが可能になりました。本件判決は特許権者に新たな道を開くものであり、司法競争の時代において各国裁判所およびUPCが果たす役割に広範な影響を及ぼす可能性があります。
2.事件の背景
(1)EU域内の各国裁判所の裁判管轄権
今日ではUPCがEU加盟国の半数以上をカバーするワンストップショップの裁判所として機能していますが、UPCが設立されるずっと以前から、特許訴訟において有利な判決が期待できる裁判所を選択して訴訟を提起するフォーラムショッピングが広く行われてきました。
EU域内の裁判管轄権は、ブリュッセルI bis規則(Regulation(EU)1215/2012)(以下、「規則」)によって規定されています。特に、特許侵害の主張に基づく訴訟は、規則によれば以下の裁判所に提起することができます:
・侵害行為が行われたEU加盟国の裁判所(規則の第7条第2項[i])
・被告の居住国である(被告企業の本社、中央管理部門、または主たる営業所が存在する)EU加盟国の裁判所(規則の第4条第1項[ii])
後者の選択肢、すなわち侵害者の居住国の裁判所で訴訟を起こすという選択肢は、原則として、1つの侵害訴訟において、当該居住国で有効化された欧州特許の国内部分に対してだけでなく、同一の欧州特許から有効化された他国の国内部分に対して、あるいは併存する他国の外国特許に対してさえ、侵害を主張する道を開くものであります。
ただし、欧州特許庁(EPO)の異議申立手続を除き、特許の有効性は、特許が登録されているEU加盟国の裁判所においてのみ争うことができます(規則の第24条第4項[iii])。この規定は、有名なGAT v LUK事件判決[iv]においてCJEUが判示した内容を成文化したものであり、有効性の争点が訴訟によって提起されたかまたは抗弁として提起されたかについては、何ら違いはありません。EU域内の被告は、自国の裁判管轄域において、自国だけでなく外国での特許の侵害についても訴えられる可能性がありますが、GAT v LUK事件判決の一般的な解釈によれば、そのような事件の被告が当該特許の無効の主張をすれば、被告の自国裁判所が外国特許部分の有効性について裁判管轄権を有さないだけではなく、外国特許部分の侵害についても裁判管轄権を失うリスクを原告が負うことになるとされていました。
(2)UPCの裁判管轄権
同じ原則がUPCにおける訴訟にも適用され、UPCも規則の第71条[v]およびUPC協定第31条[vi]に従って管轄権を決定します。
3.事件の経緯
(1)訴えの提起
ドイツの企業であるBSH Hausgeräte GmbH(以下、「BSH社」)は、複数のEU加盟国と、英国およびトルコというEU非加盟国との双方で有効化された欧州特許(以下、「本件欧州特許」)を所有しています。BSH社は、スウェーデンの企業であるElectrolux AB(以下、「Electrolux社」)が本件欧州特許が有効化されたすべての国(EU加盟国・非加盟国を問わず)の国内部分を侵害しているとして、Electrolux社に対する包括的な特許侵害訴訟をその自国裁判所であるスウェーデンの裁判所に提起しました。
(2)被告の主張
被告であるElectrolux社は、本件欧州特許の国内部分のうちスウェーデン以外の国で有効化された国内部分はスウェーデンでは効力を有さず、したがってスウェーデンの裁判所には、これらのスウェーデン国外での特許侵害の訴えに対する裁判管轄権がない、と主張しました。この主張に関してElectrolux社は、特許の有効性に関する問題については特許が登録された国の裁判所に専属管轄権を与えるとした規則の第24条第4項を根拠としました。
(3)第一審の判断
スウェーデンの第一審裁判所は、本件欧州特許のスウェーデン以外の国の国内部分の侵害に対する裁判管轄権がないと宣言しました。BSH社は、スウェーデンの控訴裁判所に控訴しました。
(4)控訴裁判所によるCJEUへの付託
スウェーデンの控訴裁判所は、規則の第4条第1項と第24条第4項との相互作用に関する重要な問題をCJEUに付託しました。CJEUはEUの最高司法機関であり、EU加盟国の国内裁判所の要請に応じて、EU法(本件で争点となったEU域内の裁判管轄権に関するブリュッセルI bis規則を含む)に関する紛争を審理し、先行して予備的判決を下す役割を有しています。CJEUは、EU法の解釈に関しては最高権限を持ちますが、EU各国の国内裁判所の独立性を尊重し、国内裁判所との協力関係によりEU法の一元的解釈と適用を確保することを目的としています。また、CJEUとUPCとの関係についても、UPCは、EU加盟国の国内裁判所の場合と同様に、CJEUと協力してEU法を十分に尊重し適用しなければなりません。UPCは、裁判管轄権のようなEU法の解釈についての予備的な先行判決をCJEUに請求することで、CJEUの判例法の優位性を尊重することになっています。
規則の第4条第1項は、EU加盟国の裁判所に、その領域内に住所を有する個人または企業が行ったすべての侵害行為(侵害が発生した場所に関係なく)に対する一般的な裁判管轄権を与えています。本件訴訟の重要な質問の1つは、規則第24条第4項に照らして、EU域内での特許侵害に関する包括的訴訟を審理する裁判所は、特許無効の抗弁が提起された場合に外国部分に関する侵害訴訟の管轄権を失うかどうか、という問題でした。
4.CJEUの判断
(1)ロングアーム(遠くまで及ぶ)管轄権(long arm jurisdiction)と特許無効の抗弁
CJEUは、規則の第24条第4項は狭義に解釈する必要があることを明確にしました。CJEUによると、規則第24条第4項で言及されている「特許の有効性(validity of patents)」は、「国際法上の対世的効果(with effect erga omnes)」を伴う特許の無効化につながるであろう有効性に関する異議申立にのみ関係します。このような対世的効果を伴う有効性の訴訟は、特許の登録地の管轄裁判所(たとえば、欧州特許のドイツ部分の場合はドイツ連邦特許裁判所)に提起する必要があります。
CJEUは、規則第24条第4項は、特許侵害訴訟で提起される当事者間の無効の抗弁には適用されないと考えています。その結果、規則第4条第1項によれば、侵害訴訟が審理されているEU加盟国の裁判所は、他のEU加盟国または第三国(非EU国)における特許侵害について判決を下すことができ、無効抗弁が提起されても管轄権を失うことはありません。したがって、特許権者はEU加盟国の国内裁判所において(同様にUPCにおいて、そしてUPCに参加していない国においてさえも)国境を越えた差止命令を取得でき、侵害者が無効抗弁を主張した場合でも当該裁判所は管轄権を持ち続けます。
EU外部の第三国(たとえば英国、スイス、トルコ)が関係する場合、被告の自国裁判所であるEU侵害裁判所は、当事者間効果を伴う無効抗弁について判決を下す管轄権を持つこともあります。これは、被告が無効の抗弁に基づいて侵害訴訟を却下する決定を得ることができることを意味します(ただし、そのような無効決定には対世的効果がないため、特許が全部または一部取り消されることはありません)。
(2)判決の意義
本件判決は、被告が特許無効の抗弁を主張した場合、国境を越えた差止命令が阻止されるというCJEUの以前の判決例からの転換を示しています。本件判決は、世界的な特許訴訟戦略にも大きな意味を持ちます。
被告は、無効抗弁を主張することで、特許権者が選択した法廷から簡単に逃れることはできません。被告は、特許または欧州特許の関連する国内部分が登録されている国において別の無効訴訟を提起することはできますが、被告が特許を侵害したかどうかという問題に対する管轄権は被告の自国裁判所すなわちEUの侵害裁判所が保持します
特許権者は、EUに拠点を置く被告を、(場合によっては世界中の)どの国における特許侵害についても、被告居住地の国内裁判所に訴えることができます。特許侵害の問題は、適用される外国法に基づいて判断される必要があります。これには、外国法(クレーム解釈などの問題)に関する、およびEUの国内裁判所が米国法や中国法などの外国法をどのように解釈し適用するかについての不確実性に関する、多国籍訴訟チームや専門家の意見が必要になる可能性があります。少なくとも原則的には、CJEUの本件判決により、EUの裁判所は特許侵害事件を世界規模で裁定することができます。
オプトアウトされていない欧州特許の所有者は、UPCシステムの一部ではない欧州特許条約(EPC)締約国(スペインやトルコなど)での侵害行為に関しても、UPC締約国に居住する被告を特許侵害で訴えることができるようになりました。この問題については、CJEUの本件判決よりも前に公表されたUPCデュッセルドルフ地方部の2025年1月28日の判決(UPC_CFI_355/2023事件)ですでに前例があります。この判決で、UPCは、無効抗弁が提起されているにもかかわらず、かつ英国がUPCシステムの一部ではないにもかかわらず、英国における欧州特許の侵害と主張された行為に対してロングアーム管轄権を認めました。この件につきましては、2025年4月4日付け配信の弊所HPの「国・地域別IP情報」の「欧州」の記事「UPC協定の非締約国で有効化された欧州特許に関する侵害訴訟についてUPCが裁判管轄権を有すると判示したUPCデュッセルドルフ地方部判決」において詳細に説明しておりますのでご参照ください(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/13317/)。
CJEUは、国内裁判所およびUPCに広範な管轄権を与えましたが、侵害裁判所は他のEU加盟国における無効訴訟を検討しなければならないことを認めました。CJEUのアプローチによれば、侵害裁判所は、例えば、外国特許の有効性に関する他のEU加盟国で係属中の無効訴訟を分離し、当該無効訴訟において当該特許が無効と宣言される合理的かつ無視できない可能性を認める場合に、侵害訴訟の停止を命じる可能性があります。その結果、特許権者が、複数の国における特許侵害に対する訴訟を1つの国内裁判所のみに提起することを決定した場合、被告は複数の国内裁判所に複数の無効訴訟を同時に提起しなければならない可能性があります。これは相当な訴訟費用を前払いする必要を生じさせ、被告に大きなプレッシャーを与える可能性があります。
5.実務上の留意事項
CJEUの本件判決は、UPC非締約国で発生した侵害の申し立てに対して裁定するUPCの権限を強化します。ただし、本件判決により、特に1つの国に居住する被告が複数の国で侵害行為をしているような国境を越えた訴訟事件において、EUの国内裁判所がUPCと競合することも可能になります。CJEUは本件判決で、EU加盟国の国内裁判所およびUPCの両方のロングアーム管轄権を確認し、無効抗弁を提起しても侵害裁判所の管轄権がなくなるわけではないことを確認しました。
特許権者は、主張する欧州特許の複数の部分がUPCのように単一の取消反訴で無効にされるリスクなしに、EUの国内裁判所に国境を越えた差止命令を求めることができるようになりましたが、侵害訴訟手続の停止のリスクは高くなります。したがって、UPCは特許権者にとってさらに魅力的な裁判地になりましたが、国内裁判所とのさらなる競争に直面する可能性があります。特許権者は、複数国を指定し、国境を越えた差止命令を求める際に、EUの国内裁判所とUPCとのどちらかを選択できるようになり、フォーラムショッピングの可能性が高まります。CJEUの本件判決により、複数の裁判管轄域で並行して訴訟が行われる可能性もあり、両当事者にとって訴訟の複雑さが増大します。
ここで、UPCはより低コストで迅速な判決を提供します。CJEUは、UPCが非UPC締約国(英国、スペイン、スイス、トルコなど)で有効化された欧州特許に関連する侵害問題を裁定する権限を持っていることを確認したため、UPCは、特に世界的な特許ポートフォリオを持つ特許権者にとって、より魅力的な選択肢です。全体として、CJEUの本件判決により、欧州特許訴訟におけるUPCの役割が強化されましたが、国境を越えた特許訴訟戦略に影響を与える可能性のある新しい原動力も導入されました。
この判決は、世界的な特許訴訟におけるEUの裁判所の重要性を強化し、国境を越えた戦略の必要性を強調するものです。EU非加盟国の裁判所もロングアーム管轄権を認めるかどうかは、時が経てば判明するものと思われます。
[情報元]
1.McDermott Will & Emery IP Update | March 6, 2025 “CJEU Recognizes Cross-Border Jurisdiction of National Courts, Long-Arm Jurisdiction of UPC”
(https://www.ipupdate.com/2025/03/cjeu-recognizes-cross-border-jurisdiction-of-national-courts-long-arm-jurisdiction-of-upc/?utm_campaign=EM%20-%20IP%20Update%20-%202025-03-06%2014%3A00&utm_medium=email&utm_source=Eloqua)
2.HOFFMANN EITLE QUARTERLY:“BSH v Electrolux – The Gateway to a New Age of Cross-Border Litigation?”
(https://www.hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2025-03.pdf#page=22)
3.Judgment of the Court (Grand Chamber) of 25 February 2025.
BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB(CJEU本件判決原文)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62022CJ0339)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊
[i] ブリュッセルI bis規則第7条第2項は以下のように規定しています。
“A person domiciled in a Member State may be sued in another Member State:
………..
(2)in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur;”
[ii] ブリュッセルI bis規則第4条第1項は以下のように規定しています。
“1. Subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State.”
[iii] ブリュッセルI bis規則第24条第4項は以下のように規定しています。
“The following courts of a Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of the domicile of the parties:
………
(4) in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an instrument of the Union or an international convention deemed to have taken place.
Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that Member State;”
[iv] 2006年7月13日ECJ(欧州司法裁判所)判決番号C-4/03, EU:C:2006:457
[v] ブリュッセルI bis規則第71条は以下のように規定しています。
“1. This Regulation shall not affect any conventions to which the Member States are parties and which, in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments.
2. With a view to its uniform interpretation, paragraph 1 shall be applied in the following manner:
(a) this Regulation shall not prevent a court of a Member State which is party to a convention on a particular matter from assuming jurisdiction in accordance with that convention, even where the defendant is domiciled in another Member State which is not party to that convention. The court hearing the action shall, in any event, apply Article 28 of this Regulation;
(b) judgments given in a Member State by a court in the exercise of jurisdiction provided for in a convention on a particular matter shall be recognised and enforced in the other Member States in accordance with this Regulation.
Where a convention on a particular matter to which both the Member State of origin and the Member State addressed are parties lays down conditions for the recognition or enforcement of judgments, those conditions shall apply. In any event, the provisions of this Regulation on recognition and enforcement of judgments may be applied.”
[vi] UPC協定第31条は以下のように規定しています。
“The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation
(EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention)”