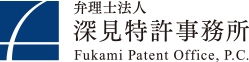クレームのソフトウェア用語がMPFクレームの適用を引き起こしたと判断した地裁判決を支持したCAFC判決紹介
米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、ソフトウェア用語が、構造的な意味を含むことなく単に機能的限定のために用いられる用語であってAIA改正前の米国特許法112条第6段落(以下、「旧112条6項」と記す)[i]の適用を引き起こす「その場限りの用語(nonce term)」[ii]、すなわち、ミーンズ・プラス・ファンクション(Means-Plus-Function:以下、「MPF」)クレームの要素であると判断した地方裁判所の判決を支持しました。さらに、CAFCは、特許明細書にはクレームに対応する構造が十分に記載されておらず、クレーム要素が不明確であると判断しました。
Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc., Case No. 23-2312 (Fed. Cir. Apr. 30, 2025) (Prost, Taranto, Stark JJ.)
1.事件の経緯
(1)訴えの提起
Fintiv, Inc.(以下、「Fintiv社」)は、「モバイルウォレットプラットフォーム」、「モバイル金融サービスプラットフォーム」、または「電子決済システム」としても知られているクラウドベースの取引システムに関連する以下の4件の特許を所有しています。
・米国特許第9,892,386号(以下、「’386特許」)
・米国特許第11,120,413号(以下、「’413特許」)
・米国特許第9,208,488号(以下、「’488特許」)
・米国特許第10,438,196号(以下、「’196特許」)
Fintiv社は、これら4件の特許(以下、「本件特許」と総称)を侵害したとして、PayPal Holdings, Inc.(以下、「PayPal社」)をテキサス州西部地区連邦地方裁判所(以下、「地裁」)に訴えました。
(2)争点となったクレームの記載
地裁は、本件特許のクレーム解釈に際して、「支払ハンドラー(payment handler)」および「支払ハンドラー・サービス(payment handler service)」というクレーム用語が不明確であるとの判決を下しました。「支払いハンドラー」に関するこれらのクレーム用語(太字で表記)が現れる本件特許のクレーム中の該当部分を以下に抜粋して示します。
**********
‘386特許のクレーム1-3
“a payment handler service operable to use [application programming interfaces (“APIs”)] of different payment processors including one or more APIs of banks, credit and debit cards processors, bill payment processors.”
‘413特許のクレーム1(クレーム2も類似)
“a payment handler configured to use APIs of different payment processors including one or more APIs of banks, credit and debit cards processors, and bill payment processors.”
‘488特許のクレーム1および’196特許のクレーム1
“a payment handler that exposes a common API for interacting with different payment processors.”
**********
(3)地裁の判断
地裁は、本件特許のクレームにおける「支払いハンドラー」という用語は、米国特許法旧112条6項に規定されるMPFクレームの限定であると結論付けました。クレームには「ミーンズ(means)」という言葉は使用されていませんでしたが、地裁は、「支払いハンドラー」という用語が典型的なMPFクレームの文言と整合した形式でドラフトされており、MPFクレームの「ミーンズ」という用語が実質的に「支払ハンドラー」に置き換えられている、と判断しました。
地裁はさらに、本件特許の明細書には、クレームされた機能を実行できる対応する構造が開示されていないと判断しました。結果として、地裁はクレームが不明確であるため無効と判断し、最終判決を下しました。
Fintiv社は地裁の判決を不服としてCAFCに控訴しました。
2.MPFクレームの解釈について
MPFクレームの解釈と実務について概要を説明いたします。AIA改正後の現米国特許法112条(f)(本件判決ではAIA改正前の対応する112条6項が適用)の規定によると、組合わせに係るクレームの要素は、構造、材料またはそれを支える作用を記載することなく、特定の機能を遂行するための手段または工程として記載することが認められており、特に典型的なMPFクレームでは、“means for・・・ing”の形式を用いて構成要素を機能的に表現します。さらに同項の規定によると、MPFクレームの保護範囲は、明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびそれらの均等物を対象とするものとされています。したがって、クレームがMPFクレームと認定された場合に、クレームされた機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていなければ、AIA改正後の現米国特許法112条(b)(本件判決ではAIA改正前の対応する112条2項が適用)の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされます。
このようにクレームがMPFクレームと認定されると権利化や権利行使に大きな影響を及ぼす場合があるため、米国特許出願のクレームをドラフトする際にはMPFクレームと認定されるのを回避するために、クレームにおいて「ミーンズ(means)」という用語は使用しないようにすることが一般的です。本件特許の「支払いハンドラー」のように「ミーンズ」という言葉を明示的に使用していないクレーム用語はMPFクレームの適用を引き起こさないという推定が働きますが、この推定は反証可能であり、特許の無効を申し立てる者が、当該クレーム用語が「十分に明確な構造」を欠く「その場限りの用語」であること、または当該クレーム用語が機能を規定しているだけでその機能を果たすのに十分な構造を提供していないこと、を立証できた場合には、その推定は覆るという実務慣行が形成されてきました[iii]。
CAFCは、本件判決においても議論されている近時のDyfan v. Target事件(以下、「Dyfan事件」)判決[iv]において、クレームがどのような場合にMPFクレームと認定されるのかについて、特にクレームに「ミーンズ」という用語が無い場合の取り扱いについてその考え方を説明しています。[v]
Dyfan事件においては、第一審の地裁は、クレームの「システム」という言葉は「ミーンズ」という言葉の代用の「その場限りの用語」であって構造の名称とは認識されず、言葉で表した構成概念であるとし、「システム」と言う言葉を使ったクレームをMPFクレームと認定しました。これに対して控訴審のCAFCは、「システム」という言葉自体は「その場限りの用語」ではあり得るが、Dyfan事件においてはクレームに記載された限定の各々が「システム」の構造的な構成要素を表し、「システム」が特有の構造を含むことことをクレームの文言自体が規定しているとし、MPFクレームと認定した地裁の判断に同意しませんでした。このように、クレームをどのように記載すれば確実にMPFクレームとの認定を回避できるのかについて様々な議論がなされてきました。
3.本件控訴審におけるFintiv社の主張の概要
Fintiv社は、地裁が、「支払ハンドラー」というクレーム用語が米国特許法旧112条6項の適用を引き起こし、そして明細書にはクレームされた機能に対応する構造が開示されていないと結論付けたのは誤りである、と主張しました。その根拠として具体的には以下の(ⅰ)~(ⅴ)の主張を行いました。
(ⅰ)「ハンドラー」という用語および「支払いハンドラー」という用語自体が全体として構造を特定している
(ⅱ)インターネットのような外部ソースが、「支払いハンドラー」という用語が全体として構造を示しているという主張をサポートしている
(ⅲ)争われているクレームにおける“that”、“operable to”、“configured to”のような接続語は、非構造的な用語よりも、よりしばしば構造的な用語に使用される
(ⅳ)Dyfan事件が本件においても適用される
(ⅴ)クレームの文言が「支払いハンドラー」の入力、出力、および動作を規定している
4.CAFCの判断
CAFCは、「ミーンズ」という言葉を明示的に使用していない「支払ハンドラー」という用語を分析しました。そして、CAFCは、「支払いハンドラー」というクレーム用語が機能を規定しているものの、Dyfan事件とは異なり、その機能を遂行するのに十分な構造をクレームが規定しておらず、当業者に十分な構造を伝えていないないため、当該用語はMPFクレームの適用を引き起こさないという推定についてPayPal社が反証することに成功したと判断しました。
以下に、Fintiv社が控訴審において提起した上記の主張(ⅰ)~(ⅴ)についてCAFCがその主張を拒絶した理由について説明いたします。
(1)上記主張(ⅰ)について
地裁が正しく分析したように、「ハンドラー」という用語は、CAFCが特定の機能を実行するソフトウェアやハードウェアの一般的な記載に過ぎないと判断してきた「モジュール」という言葉になぞらえることができるものであります。また、地裁は、「ハンドラー」という言葉が何ら構造を伝える言葉ではないことを示す技術的な辞書を評価して、「ハンドラー」という言葉は当業者に対して十分な構造を意味するものではなく、また「支払い」という修飾語も、単に「ハンドラー」の機能を説明するだけで、「ハンドラー」に対して何ら構造を与えるものではないと正しく判断しました。CAFCは地裁の判断に同意しました。
(2)上記主張(ⅱ)について
地裁は、たとえばFintiv社が言及したInternet Open Trading Protocol(IOTP)が、「支払いハンドラー」という用語が支払いシステムにおける異なる構造を有する異なるエンティティーを指すことができると示唆しているだけであり、「ハンドラー」単独でも「支払いハンドラー」という用語であってもクレームされた機能を実行するための構造を全体として開示していない、と判断しました。CAFCもこれに同意しました。
(3)上記主張(ⅲ)について
Fintiv社は、その主張の根拠として同様の接続語を用いた以前の判決例を数件挙げましたが、このように別の特許に関する事件での接続語が本件クレームの接続語と同じであると言うこと以外に、なぜそのような先行事例の接続語が本件において影響を及ぼすのかについて、Fintiv社は有意義な説明をしていないとCAFC判決は判断しました。
(4)上記主張(ⅳ)について
Dyfan事件の控訴審判決においてCAFCは、「システム」という言葉自体は「その場限りの用語」ではあり得るが、当業者であれば、クレームを構成する限定である「コード」、「アプリケーション」が構造のクラスを示しており、記載されたクレームの機能が市販のコードまたはアプリケーションを用いて実現可能であることを知っていたであろうとして、特許の無効を主張する当事者が、当該クレームが機能を規定しているだけでその機能を果たすのに十分な構造を提供していないことを立証できなかったため、「ミーンズ」を用いないクレーム用語はMPFクレームの適用を引き起こさないという推定について反証できなかった、と判示しました。
これに対して本件においてCAFCは、本件特許のクレームで用いられている「支払いハンドラー」という用語は、「ミーンズ」の代替として機能する構造のブラックボックスに過ぎず、当業者はクレームに記載された機能をどのように実現するのか理解できなかったであろう、と認定しました。この結果、当該クレームが機能を規定しているだけでその機能を果たすのに十分な構造を提供していないことを立証できたため、「ミーンズ」を用いないクレーム用語はMPFクレームの適用を引き起こさないという推定について反証されたと結論付けました。
(5)上記主張(ⅴ)について
Fintiv社は、この主張をサポートするために以前の裁判例を引用しましたが[vi]、CAFCは、本件特許においては、クレーム、明細書、図面のいずれも支払いハンドラーの「入力、出力、接続、動作」について十分明確な構造を提示していない、と指摘しました。
5.CAFCの最終結論
CAFCは、上記のように「支払いハンドラー」という用語が米国特許法旧112条6項の適用を引き起こすと判断した後、「支払いハンドラー」の機能の遂行に関する対応する明細書に記載されている構造を特定しようとしたが、何も見つけられませんでした。CAFCは、「これらの機能を実現するアルゴリズムがなければ、そしてより一般的には、十分に対応する構造を明細書が明らかにしていないことを考慮すると、支払いハンドラーという用語は不明瞭である」との最終結論を下しました。
6.実務上の留意点
MPFクレームと解釈される不利益を回避するために出願の段階でMPFクレームと解釈されないクレームドラフティングを心がける必要があります。Williamson事件、Dyfan事件など過去の裁判例を見てみると、CAFCはたとえば「モジュール」という限定は実行する機能を記述するだけで、これを修飾する文言は何ら「モジュール」に構造を与えるものではないと判断しました。このように、「ミーンズ」の代用に「モジュール」や「ユニット」のような一般的な単語を用いるだけでは、そのようなクレーム限定は構造を与えるものではないとの被告の反証によって、MPFクレームではないという推定が反証される恐れがあります。
そのような反証に耐えるためには、その用語自体が直接的にハードウェア構造を規定している用語(たとえば「回路」という用語)を使用することや、ソフトウェア関連発明の分野においてはDyfan事件判決において示唆されたように当業者であれば特定の構造として理解したであろう既存のプログラム/コードを選択することができる用語を使用することが考えられます。一方、MPFクレームであると認定され、明細書にクレームの機能を実行する構造が具体的に記載されていなければ、そのクレームは明確性違反と判断され、拒絶理由、無効理由となってしまいます。万が一MPFクレームと認定された場合に備えて、クレームされた機能を実行する構造(特にソフトウェア関連発明においては、クレームされた特有の機能を汎用コンピュータに実行させるためのアルゴリズム)を明細書に十分開示しておく必要があります。より広い権利範囲を確保するためにもできるだけ多くの実施形態や変形例を開示しておくべきでしょう。
[情報元]
1.McDermott Will & Emery IP Update | May 8, 2025 “‘Payment Handler’: A Nonce Term Without Instructions”
(https://www.ipupdate.com/2025/05/payment-handler-a-nonce-term-without-instructions/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EM%20-%20IP%20Update%20-%202025-05-08%2014%3A00&utm_content=post_title)
2.Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc., Case No. 23-2312 (Fed. Cir. Apr. 30, 2025) (Prost, Taranto, Stark JJ.)(判決原文)(https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2312.OPINION.4-30-2025_2506759.pdf)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊
[i] 本件訴訟は、AIA施行日である2013年3月16日よりも前の出願日を有する特許を対象とするものであり、本件訴訟はAIA改正前の旧法の適用になるため、本稿では旧法の112条6項に言及しますが、この条項はAIA改正後の現行法の112条(f)と全く同じ内容です。
[ii] 後述するDyfan事件判決では、CAFCは“nonce word”について、“system may be a nonce word used as a substitute for the word means.”と定義しました。
[iii] Williamson, 792 F.3d at 1348
[iv] Dyfan, LLC v. Target Corp., 28 F.4th 1360, 1369–70 (Fed. Cir. 2022);
[v] Dyfan事件の詳細については、拙稿「『ミーンズ』を欠くクレーム限定がMPF解釈を回避できると判断したCAFC判決」(知財管理 Vol. 73 No. 7 2023)をご参照ください。
(https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/202307_chizaikanri.pdf)
[vi] Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)