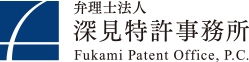特許権の効力範囲が争点となった、同日言渡しの2件の大法院判決紹介
2025年5月15日付で、特許権の効力範囲が争点となった、2件の大法院判決が言い渡されました。そのうちの1件は「直接・間接侵害」、他の件は「存続期間が延長登録された特許権」に関しており、いずれも特許実務に直結する興味ある重要な判決であることから、以下それぞれについて概要を紹介し、併せて、これらの判決から導かれる実務上の留意点に言及します。
I.海外でワクチン完成品を生産するために国内でワクチン原液を生産して海外に供給した行為について特許侵害を否定した大法院判決
1.概要
大法院は、多数の構成成分を含むワクチン組成物に関する特許権侵害差止訴訟において、韓国国内で肺炎球菌ワクチン完成品生産のための原液を生産してロシアの製薬会社に供給し、ロシアの製薬会社がロシアでワクチン完成品を製造・販売している状況で、当該ワクチン完成品を製造・販売する行為が当該ワクチン組成物に関する特許権を侵害するか否かは、特許権の属地主義の原則および構成要素完備の原則を考慮して厳格に判断すべきであると指摘した上で、特許権を侵害しないとの判決を下しました。
また、同じ判決において大法院は、当該ワクチン組成物の完成品を韓国で生産し、ロシアの他の会社が臨床試験する目的で当該他の会社に供給する場合には、試験または研究の例外規定の適用を受けて特許権の効力が及ばないと認定しました(大法院2025.5.15.宣告2025Da202970判決)。
2.事件の背景
(1)本件特許の概要
本件判決の対象となる特許(以下「本件特許」)は、「13個の血清型の肺炎球菌莢膜多糖類がそれぞれキャリアタンパク質にコンジュゲートした多糖類-タンパク質コンジュゲートを含む13価の免疫原性組成物」の発明に関しており、その請求項1の日本語訳(下記「情報元2より引用」)は次の通りです。
『[請求項1]生理学的に許容されるビヒクルと共に、13個の異なる多糖類・タンパク質接合体を含み、このとき、それぞれの接合体が、CRM197運搬体タンパク質に接合された異なる血清型のストレプトコッカス・ニューモニエ由来の莢膜多糖類を含み、前記莢膜多糖類が血清型1,3,4,5,6A,6B,……19A,19Fおよび23F(13種の血清型を特定しています)から製造される、肺炎球菌ワクチンに用いられるための13価免疫原性組成物。』
(2)本件訴訟の当事者
本件特許の専用実施権者は、本件特許発明の免疫原性組成物の実施製品である13価の肺炎球菌多糖類ワクチンについて韓国食品医薬品安全処から許可を受け、本件特許の特許権者から当該ワクチンを輸入して韓国で販売しています。
本件訴訟の被疑侵害者(第1審であるソウル地方法院の裁判における被告)は、13価の肺炎球菌多糖類ワクチンについて研究および生産準備を完了し、ロシアの製薬会社と前記ワクチンに対するライセンスおよび供給契約を締結しました。この契約に従い、被疑侵害者は、各13個の血清型の多糖類-タンパク質コンジュゲートが個別に包装された13種類の個別コンジュゲート原液をロシアの製薬会社に提供しました(以下、「実施行為1」)。
また、これとは別に、被疑侵害者は、13種類の個別コンジュゲート原液を混合および製剤化して人体に注入できる薬物が入った注射器の完成品形態で生産した後、これを臨床試験用としてロシアの製薬会社に4回提供し(以下、「実施行為2」)、ロシアの製薬会社はこれを使用してロシアで臨床試験を行ない、ワクチンに対する品目許可を受けました。
3.ソウル中央地方法院の判決
本件特許の特許権者および専用実施権者(以下「特許権者ら」とします)は、被疑侵害者の実施行為1が本件特許に対する直接侵害または間接侵害(特許法第127条第1号[i])を構成し、実施行為2が本件特許を直接侵害したと主張して、被疑侵害者を相手取ってソウル中央地方法院に特許権侵害差止訴訟を提起しました。
上記「実施行為1」に関して、上記ロシアの製薬会社がロシアで製造・販売するワクチン完成品が本件特許請求項1の権利範囲に属するという点、および、上記「実施行為2」に関して、被疑侵害者がロシアの製薬会社の臨床試験のために生産した完成品ワクチンが本件特許の請求項1の保護範囲に属するという点については、当事者間に争いはありませんでした。よって本件の争点は、被疑侵害者による「実施行為1」および「実施行為2」が、本件特許の請求項1の侵害に当たるか否かに絞られます。
(1)実施行為1について
まず、実施行為1が直接侵害を構成するか否かに関連して、ソウル中央地方法院は、既存の大法院判例(大法院2019.10.19.宣告2019Da222782、222799(併合)判決、以下「半製品関連事件大法院判決」とします)[ii]における以下の判断基準、すなわち、以下の(i)~(iv)の場合には、特許権の実質的保護のために、国内で特許発明の実施製品が生産されたものと等しいと見なされるという基準を引用しました。
(i)国内で特許発明の実施のための部品または構成の全部が生産されるか、大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産され、
(ii)これが1つの主体に輸出され、最後の段階での加工・組立が行われることが予定されており、
(iii)そのような加工・組立が極めて些細または簡単であって、
(iv)前記のような部品全体の生産または半製品の生産だけでも、特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を実現できる状態に至った場合。
このような基準に即して、ソウル中央地方法院は、13種類の個別コンジュゲート原液がそれぞれ免疫原性を確保できるように製造されたはずであるので、これを混合するだけで13価の免疫原性が発現されると見られ、また、本件特許の明細書の記載とワクチン分野の通常の知識に照らしてみると、混合工程は通常の技術者にとって技術的困難性がないと判断されるので、被告が13種類の個別コンジュゲート原液を生産しただけでも、国内で本件特許発明の各構成成分が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態が備えられたと見なすのが妥当であると述べて、被告の実施行為1が直接侵害を構成すると認めました。
(2)実施行為2について
実施行為2について、ソウル中央地方法院は、特許権の効力が及ばない範囲を規定する特許法第96条第1項第1号[iii]における研究または試験は、特許発明を実施する主体のための研究または試験を意味するのに対し、本件では、被疑侵害者が本件特許に係る物を生産し、被疑侵害者ではないロシアの製薬会社が自らの利益のために研究または試験を行なったものであるので、被疑侵害者の実施行為2は、特許法第96条第1項第1号で規定する特許権の効力が及ばない範囲に該当せず、本件特許に対する直接侵害を構成すると判断しました。
4.特許法院の判決
上記ソウル中央地方法院の判決に対して被疑侵害者は、特許法院に控訴しました。控訴審において、特許法院は、以下の理由により、ソウル中央地方法院の判決を取り消し、特許権者らの特許権侵害差止請求を棄却しました。
(1)実施行為1について
まず、実施行為1について、特許法院は、両当事者が提出した証拠によると、13価の個別コンジュゲート原液の混合工程が極めて些細または簡単であるといえず、13種類の個別コンジュゲート原液を単に混合するだけで13価の免疫原性が具現される状態であると見られないので、実施行為1が本件特許に対する直接侵害を構成しないと判断しました。
また、特許法院は、13種類の個別コンジュゲート原液が全てロシアに輸出され、外国で完成品が生産されたので、本件特許に対する間接侵害も成立しないと判示しました。
(2)実施行為2について
次に、実施行為2について、特許法院は、特許法第96条第1項第1号は、試験的実施の例外を認めて技術発展の促進を図るための趣旨の規定であり、外国で医薬品の品目許可を取得して究極的に商業的利益を得る目的であるとしても、前記規定の適用が排除されないと指摘しました。そこで、特許法院は、実施行為2が特許法第96条第1項第1号により特許権の効力が及ばない範囲に属するので、原告の特許を侵害しないと判断しました。
5.大法院の判決
上記特許法院の判決に対して、特許権者らは大法院に上告し、上告審において大法院は、原審の判断に誤りはないとして、上告を棄却しました。その理由は以下の通りです。
(1)実施行為1について
まず、実施行為1に関して、大法院は、上記半製品関連事件大法院判決で示した判断基準を改めて言及しつつも、このような場合に該当するか否かは特許権の属地主義の原則と構成要素完備の原則を考慮して厳格に判断すべきであることを強調しました。
具体的には、本件では、海外で生じるワクチン完成品の製造行為が極めて些細であるか簡単であって部品の生産または半製品の生産だけでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態になるか否かが争点となりましたが、特許法院は、(i)前述の半製品関連事件大法院判決において最終的に糸支持体を形成するのは結び目の形成という単一工程であってその操作が非常に単純であるのに対し、本事案における混合工程は各個別の接合体原液の投入量、混合比率、混合順序、適切な混合条件(温度、時間、速度、pH等)を精密に制御して行われるという面で両事案には差があり、(ii)本事案において混合工程が正しく行われなければ本件特許発明の作用効果である13価免疫原性が具現されない可能性もあるという点を挙げて特許侵害を否定し、大法院は特許法院の判断を支持しました。
なお、大法院は、特許権の属地主義の原則に従って、間接侵害における最終製品の「生産」とは国内での生産を意味するため、生産が国外で行われる場合には間接侵害が成立しないことを明らかにしました。
(2)実施行為2について
実施行為2について、大法院は、特許法第96条第1項第1号は発明の保護と発明の利用促進との間に調和とバランスを図るための規定であるので、特許権者の正当な利益も併せて考慮する必要があるものの、研究または試験を目的とする実施行為2が特許権者または専用実施権者の独占的・排他的利益を不当に毀損したと見ることは困難であるため、実施行為2には特許法第96条第1項第1号により特許権の効力が及ばないと認定しました。
II.最初の許可適用症に限らず、その後に許可された異なる適応症であっても、医薬用途が実質的に同一である場合には、存続期間が延長された特許権の効力範囲に含まれると認定した大法院判決
1.概要
韓国特許法院は、消極的権利範囲確認審判の審決取消訴訟において、存続期間が延長された特許権の効力範囲を判断するにあたり、確認対象発明の治療効果および用途が薬事法上、最初に許可された効能・効果と同一である必要はなく、特許発明の明細書等を参酌して特許発明の治療効果および医薬用途と実質的に同一か否かを中心に判断すべきであるという判決を下しました(特許法院2025.1.23.宣告2024Heo13541判決)。本件は大法院に上告されましたが、審理不続行で上告が棄却[iv]され、特許法院判決が確定しました(大法院2025.5.15.宣告2025Hu10142判決)。
2.事件の背景
(1)存続期間が延長された場合の特許権の効力
韓国特許法第95条[v]には、存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由となった許可等の対象物についての当該特許発明の実施行為にのみ及ぶと規定されています。ただし、その許可等において、物について特定の用途が定められている場合には、当該用途に用いられる物に特許権の効力が及びます。
一方、存続期間が延長された特許発明の権利範囲に確認対象発明が属するかは、有効成分の同一性の他にも、その治療効果と用途が同一であるか否かにかかっています。これを巡り、前記「用途」を薬事法上、最初に許可された適応症のみに限定すべきかについての議論がありました。
(2)本件の当事者、および、消極的権利範囲確認審判の請求について
(a)当事者の概要
本件特許の特許権者は、胃食道逆流症の治療に用いるためのクロマン置換されたベンゾイミダゾール誘導体に関する医薬発明について特許を受け、専用実施権者は、まず以下の2つの適応症に適応する医薬品について品目許可を得ました。
適応症➀:びらん性胃食道逆流症
適応症②:非びらん性胃食道逆流症
また、この許可を得るために要した時間について、本件特許の存続期間の延長登録が認められました。その後、専用実施権者は、次の適応症③について効能·効果を追加する変更許可を受けました。
適応症③:消化性潰瘍および/または慢性萎縮性胃炎患者におけるヘリコバクター・ピロリ除菌のための抗生剤併用療法
(b)消極的確認審判の請求と、特許審判院の判断
これに対し、韓国のあるジェネリック薬剤製造会社(以下「ジェネリック会社」とします)は、本件特許発明と同一の有効成分を含む上記適応症③用の薬学組成物を、確認対象発明として消極的権利範囲確認審判を請求し、確認対象発明は存続期間が延長された本件特許の保護範囲に属さないと主張しました。
特許審判院は、最初に品目許可を得た適応症①および②と、追加で品目許可を得た適応症③はすべて「胃酸分泌を抑制して治療される酸関連の疾患」であって、治療効果および用途が同一であるとの理由で棄却審決を下しました。これを不服としてジェネリック会社は特許法院に控訴しました。
3.特許法院の判決
特許法院は、延長された特許権の効力範囲を判断するための基準としての特許法上の「用途」には、最初に品目許可を得た適応症だけでなく、それと実質的に同一の疾患の予防または治療に使用される医薬品の適応症までのすべてが含まれると見なすのが妥当であると認定しました。
特に特許法院は、「用途」の同一性可否は、明細書の記載等を通じて把握した特許発明の技術的意義や技術思想の核心、作用機序の同一性可否、適用対象の器官や組織等の具体的な適用部位、対象病症、処方等の使用状況等を総合的に考慮して判断すべきであると述べて、本件特許の明細書の記載に鑑みれば、本件特許は上記適応症①、②、③を含む多数の「胃酸分泌を抑制することで治療される酸関連疾患」を治療するための化合物を提供することを技術的特徴とすると判断しました。
これに基づいて、特許法院は、許可対象物の「用途」には最初に品目許可を得た適応症①および適応症②の他にも、追加で品目許可を得た適応症③も含まれると認め、確認対象発明は存続期間が延長された本件特許の権利範囲に属するという結論に至りました。
4.大法院の判決
特許権者は上記特許法院判決を不服として、大法院に上告しましたが、大法院は、上告の理由が明確な根拠を欠くものと判断し、審理を行なうことなく上告を棄却しました。その結果、上述の特許法院判決が確定しました。
III.実務上の留意点
上述した同日言渡しの2件の大法院判決から、以下の点について留意すべきことが読み取れます。
(1)上記I.の大法院判決から読み取れる留意点
(a)この大法院判決の原審である特許法院判決では、上述の「半製品関連事件大法院判決」において被疑侵害者の国内生産行為に対して特許侵害を認めたのに対して、本事案においては、本件特許発明の作用効果が具現化されるように原液の混合工程が適切に行われることの困難性を挙げて、特許侵害を否定しました。
国内における半製品の生産だけで特許侵害が認められるほどに海外での最終加工行為が極めて些細若しくは簡単であるかどうかの判断は容易ではなく、過去の半製品関連事件においても侵害を認めた場合とそうでない場合が含まれており、今後の判例の蓄積を注視していく必要があります。
(b)上記Iの大法院判決からも分かるように、構成要素完備の原則の例外に当たる半製品関連事件の法理は厳格に適用されるため、特許出願人または特許権者の立場では、後日に当該発明が適用された物がいかなる態様で取引され得るのかを予想した上で、さまざまな可能性を最大限にカバーできる多様な請求項によって特許登録を受けておくことが重要といえます。
(2)上記II.の大法院判決から読み取れる留意点
存続期間が延長された特許権の効力については、国によって相違していることから、そのような特許権の侵害の成否の判断においては、国ごとの制度の詳細な相違点に十分留意する必要があります。たとえば欧米では、存続期間が延長された特許権の効力を、許可された有効成分を含有する医薬品の「すべての用途」に及ぶものとして広く認めているのに対して、韓国では、上述のように延長された特許権の効力範囲を許可対象物の「特定用途」に及ぶものと規定しています。日本においても韓国と類似の制度を有していますが、複数の許可に基づいて複数回の延長が可能である点で、最初の許可に基づいて1回のみ延長が認められる(韓国特許法第89条[vi])韓国とは異なります。(たとえば下記URLのKim&Changの2024.11.11付ニュースレター参照)
(https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=30621)
特に、今回の大法院判決で明確にされた、「延長された特許権の効力範囲を判断するための基準としての特許法上の「用途」には、最初に品目許可を得た適応症だけでなく、それと実質的に同一の適応症までのすべてが含まれる」という考え方は韓国に特有のものであることから、韓国での対応に際しては本件判決の趣旨を十分把握しておくことが重要と言えます。
[情報元]
1.FIRSTLAW IP NEWS_June 2025より
(1)大法院、ワクチン組成物に含まれる多数の構成成分の分離生産および販売が特許権を侵害しないと判断
(2)実質的に同一の医薬用途も存続期間が延長された特許権の効力範囲に含まれると判断
2.ジェトロソウル事務所 知財判例データベース「海外でワクチン完成品を生産するために国内でワクチン原液を生産して海外に供給した行為について特許侵害を否定した事例」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2025/_541605.html
[担当]深見特許事務所 野田 久登
[i] 韓国特許法第127条第1号は、次のように規定しています。
『第127条(侵害とみなす行為) 次の各号の区分による行為を業とする場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。
1. 特許が物の発明である場合:その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与・輸出または輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為』
[ii] 半製品関連事件大法院判決の対象物品は、外科的手術に用いられる医療用糸を体内に挿入して固定するのに用いられる医療用糸挿入施術キットです。当該事件の被疑侵害者が国内で生産している製品は、争点となった特許請求項に記載された大部分の要件を満たすものの、「糸が生体組織内に固定されるように糸の端部に糸支持体が形成される」という要件だけは、被疑侵害者の製品を使用する海外の病院での手術過程で初めて満たされます。同事案において大法院は、海外の病院での手術過程で初めて満たされる要件は結び目の形成という、単一かつ非常に単純な操作であることを理由に、被告の国内生産行為に対して特許侵害を認めました。
[iii] 韓国特許法第96条第1項第1号は、次のように規定しています。
『第96条(特許権の効力が及ばない範囲)第1項第1号:
①特許権の効力は、次の各号のいずれかに該当する事項には及ばない。
1. 研究または試験(「薬事法」による医薬品の品目許可・品目申告および「農薬管理法」による農薬の登録のための研究または試験を含む)をするための特許発明の実施』
[iv] 「審理不続行による上告棄却」とは、上告の理由が明らかな根拠を欠く場合に、審理を行なうことなく、決定で上告を棄却することを言います。
[v] 第95条(許可等による存続期間が延長された場合の特許権の効力)は、次のように規定しています。『第90条第4項により特許権の存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由となった許可等の対象物(その許可等において、物に対し特定の用途が定められている場合にはその用途に使用される物)に関するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。』
[vi] 特許法第89条(許可等に伴う特許権の存続期間の延長)
①特許発明を実施するために他の法令によって許可を受けたり登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下、“許可等”という。)のために必要な有効性・安全性等の試験によって長期間が所要される大統領令で定める発明である場合には、第 88 条第 1 項にかかわらずその実施することができなかった期間に対して5年の期間までその特許権の存続期間(第92条の5第2項により特許権の存続期間の延長が登録された場合には、その延長された日までをいう)を 1 度だけ延長することができる。ただし、許可等を受けた日から14年を超過して延長することはできない。