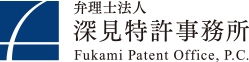CRISPRの特許に関して米国特許法第102条と第112条とでは実施可能性の基準が異なると判断した特許審判部の判断を支持したCAFC判決
米国連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、米国特許法第102条における実施可能性(他特許の新規性阻害に関わる)および第112条における実施可能性(当該特許の有効性に関わる)の基準が異なることを示し、先行技術文献に実際に行われた実施例が記載されていない場合であってもクレームの新規性を喪失させる目的においては実施可能性を有するとする特許審判部(以下「PTAB」)の判断を支持しました。
Agilent Technologies, Inc. v. Synthego Corp., 事件番号2023-2186, 2023-2187 (Fed. Cir. June 11, 2025) (Prost, Linn, Reyna, JJ.)
1.事件の背景
本判決は、生物学とバイオテクノロジーの領域を一変させた遺伝子編集技術であるCRISPR(“clusters of regularly interspaced short palindromic repeats”の略)の特許に関します。Agilent Technologies(以下「Agilent社」)は、CRISPR-Casシステムの安定性と性能を向上させるために設計された化学的に修飾されたガイドRNAに関する特許(US特許10,337,001、US特許10,900,034)を有していました。
US特許10,337,001のクレーム1は、以下のとおりです。
1. A synthetic CRISPR guide RNA having at least one 5′-end and at least one 3′-end, the synthetic guide RNA comprising:
(a) one or more modified nucleotides within five nucleotides from said 5′-end, or
(b) one or more modified nucleotides within five nucleotides from said 3′-end, or
(c) both (a) and (b);
wherein said guide RNA comprises one or more RNA molecules, and has gRNA functionality comprising associating with a Cas protein and targeting the gRNA:Cas protein complex to a target polynucleotide, wherein the modified nucleotide has a modification to a phosphodiester linkage, a sugar, or both.
(1. 少なくとも1つの5’末端および少なくとも1つの3’末端を有する合成CRISPRガイドRNAであって、以下のものを含む合成ガイドRNA:
(a) 5’末端から5ヌクレオチド以内に1つ以上の修飾ヌクレオチド、または
(b) 3’末端から5ヌクレオチド以内に1つ以上の修飾ヌクレオチド、または
(c) (a)および(b)の両方;
ここで、前記ガイドRNA(以下「gRNA」)は1つ以上のRNA分子を含むとともに、gRNA機能を有し、前記gRNA機能はCasタンパク質と会合すること、ならびにgRNA:Casタンパク質複合体を標的ポリヌクレオチドに標的化することを含み、前記修飾ヌクレオチドは、リン酸ジエステル結合、糖、またはその両方に対する修飾を有する。)
Synthego Corp(以下「Synthego社」)は、Agilent社のこれら2件の特許のすべてのクレームに対して、当事者系レビュー(IPR)を申請しました。PTABは、2014年8月20日を優先日とするPioneer Hi-Bred International社の国際公開公報(WO 2015/026885 A1)(以下「Pioneer Hi-Bred」)がAgilent社の特許と同様のgRNA機能とそれが実施可能であることを開示していること等を根拠に、Agilent社のこれら2件の特許のすべてのクレームの新規性を否定しました。Agilent社は、PTABの判断を不服としてCAFCに控訴しました。
2.CAFCの判断
Agilent社は、当該控訴において、以下の3つの観点ⅰ)~ⅲ)から、Pioneer Hi-Bredが実施可能であるというPTABの判断に異議を唱え、Agilent社の特許クレームが特許性を有する旨の主張をしました。
ⅰ)Pioneer Hi-Bredは、具体的にどのような修飾を行えばgRNA機能が得られるのかを実証することなく、単に研究計画を提案しただけである。
ⅱ)Pioneer Hi-Bredには、実際に実施された例が記載されておらず、多数の機能しない塩基配列が開示されているだけであり、当業者は過度の実験なしに成功した実施例を特定することはできない。
ⅲ)2014年当時のCRISPR技術は初期段階にあって予測不可能性が高く、当時の技術常識に基づいて当業者はPioneer Hi-Bredを実施することができない。このことについては、2023年のAmgen v. Sanofi最高裁判決(以下「Amgen事件」)において、明細書の記載がクレームの全範囲を実施可能にしていないとして広範な範囲の属クレームが無効とされたということによっても強力にサポートされる。
CAFCは、Agilent社の主張を受け入れませんでした。CAFCは、米国特許法第102条の実施可能性と第112条の実施可能性とを明確に区別しました。CAFCは、米国特許法第102条の実施可能性の基準は第112条よりも低く、先行技術文献はクレームの範囲内で単一の実施例を実施可能とするだけでよいと説明しました。
CAFCは、この区別を以下のように条文の文言と条文の目的の両方を根拠としました。すなわち、米国特許法第112条は、明細書に基づいて当業者が発明を「製造し、使用」できることを要件としています。一方、米国特許法第102条には、そのような要件が含まれていません。この相違は条文の目的の違いを反映しています。米国特許法第112条は、特許権者が開示した範囲を超えてクレームしないことを保証し、それによって過度に広範な独占を防止します。Amgen事件において、最高裁判所は、「クレームが広範になるほどクレームが要求する独占の範囲も広くなるため、実施可能としなければならない範囲も広くなる」ことを論理的根拠としました。
CAFCは、Amgen事件における最高裁判所の論理的根拠は、特許権者が米国特許法第112条に基づく属クレームの全範囲を明細書で裏付ける責任を負っていることに基づいており、米国特許法第102条には当てはまらないと説明しました。そして、CAFCは、米国特許法第102条では、先行技術文献がどの程度の範囲をクレームしているかが問題ではなく、当業者が過度の実験をせずに少なくとも1つの実施例を実施するのに十分な内容を開示しているかどうかが問題になると述べました。
CAFCは、「過度の実験」分析を規定するWands factors[1]を適用したPTABの判断を支持し、gRNAの化学修飾は周知であり、クリックケミストリー[2]などの合成技術は2014年の優先日までに確立されており、当該分野は十分に成熟していたと指摘しました。CAFCは、また、Pioneer Hi-Bredが多数の機能しない塩基配列を開示しているという事実は、Pioneer Hi-Bredの先行技術文献としての適格性を失わせるものではなく、むしろ重要なのは、当業者が過度の実験をすることなく、クレームの範囲内に含まれる少なくとも1つの実施例を製造し、使用できることであると述べました。そして、Agilent社の主張を認めず、Pioneer Hi-Bredが少なくとも1つの実施例を実施可能としており、したがってAgilent社の特許の新規性を阻害しているとのPTABの判断を支持しました。
3.実務上の留意点
本判決は、Regents of the Univ. of Cal. v. Broad Inst.(以下「Regents事件」)[3]におけるCAFC判決と併せて読むと、一貫したテーマを反映しています。すなわち、実施可能性と着想は、当業者が過度の実験をすることなく何ができるかということによって判断されるということです。
Regents事件において、CAFCは、発明者は着想の時点で発明の成功を認識する必要はないことを明確にしました。また、本判決において、CAFCは、実施可能性のために先行技術文献は実際に行われた実施例によって成功を実証する必要はないことを確認しました。
これらのCAFC判決を考慮すると、着想であれ予測であれ、開示の試金石は確実性や完全性ではなく、通常の技術と合理的な努力を用いて当業者のギャップを埋める能力であることが再確認されます。
[情報元]
1.IP UPDATE (McDermott) “CRISPR Clarity: Enablement Is Analyzed Differently Under §§ 102 and 112” June 18, 2025
https://www.ipupdate.com/2025/06/crispr-clarity-enablement-is-analyzed-differently-under-%c2%a7%c2%a7-102-and-112/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EM%20-%20IP%20Update%20-%202025-06-19%2014%3A00&utm_content=post_title
2.Agilent Technologies, Inc. v. Synthego Corp., 事件番号2023-2186, 2023-2187 (Fed. Cir. June 11, 2025) (Prost, Linn, Reyna, JJ.) 本件CAFC判決原文
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2186.OPINION.6-11-2025_2528805.pdf
[担当]深見特許事務所 赤木 信行
[1] 特許における「実施可能要件」を満たしているかどうかを判断する際に用いられる、米国特許法112条(a)に基づく評価基準の1つ。具体的には、クレームに記載された発明を実施するために、当業者がどの程度の実験を必要とするかを考慮する。
[2] 特定の条件下で、異なる分子同士を容易かつ効率的に結合させる化学反応の概念。アジドとアルキンという2種類の分子を銅などの触媒を用いて結合させる反応がよく知られている。
[3] CRISPR-Cas9遺伝子編集技術の発明に関する特許の帰属を巡るインターフェアレンス事件。Regents of the Univ. of Cal.(以下、「UC」)のJennifer Doudna教授らは2012年にCRISPR-Cas9技術の基礎的な発見を報告し、試験管内(in vitro)でのCRISPR-Cas9を用いた遺伝子編集の発明について特許を取得し、その後、Broad Institute(ハーバード大学・MIT連合)およびFeng Zhang博士ら(以下「Broad」)は、哺乳類細胞内(in vivo)でCRISPR-Cas9を用いた遺伝子編集の発明について特許を取得したが、UCはBroadの哺乳類細胞内(in vivo)の特許はUCの試験管内(in vitro)の特許から自明であるため、哺乳類細胞内(in vivo)でのCRISPR-Cas9を用いた遺伝子編集の発明についての先発明者はUCであると主張したが認められなかった。