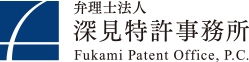UPCにおけるクレーム解釈の原則に関する最近の判決紹介
統一特許裁判所(UPC)においては、明細書の内容がクレームの範囲を理解する上で決定的に重要であるというクレーム解釈の原則が、近時のUPC控訴審判決によって示され、その後、UPCのあらゆるレベルの裁判官は、この原則を適用してUPCにおけるクレーム解釈の適用方法を形作ってきました。本稿では、このようなクレーム解釈の原則について明示したUPC控訴審判決の流れについて振り返るとともに、最近下されたUPCハンブルク地方部での判決で採用されたクレーム解釈のアプローチについて紹介いたします。
1.クレーム解釈の原則に関するUPC控訴裁判所の近時の判決の流れ
(1)NanoString Technologies Inc v 10x Genomics Inc事件
UPCの控訴裁判所(ルクセンブルク)は、2024年2月26日付けで下したNanoString Technologies Inc v 10x Genomics Inc事件(以下、「NanoString事件」)の控訴審判決(UPC_CoA_335/2023)[i]において、明細書および図面は、常にクレーム解釈のための説明的補助として使用されなければならず、クレームの文言における曖昧さを解消するためだけに使用されるべきではないという原則、すなわち、明細書および図面を検討して初めてクレームの範囲が明らかになるというクレーム解釈の原則を示しました。
より具体的に、このNanoString事件控訴審判決においてUPC控訴裁判所の採用したクレーム解釈の原則は以下の通りです。
① UPCの控訴裁判所は、欧州特許条約(EPC)第69条[ii]およびその解釈に関する議定書[iii]に従って、以下の原則に則って手続を進めるものである。
② 特許クレームは、欧州特許の保護範囲を決定するための出発点であるだけでなく、決定的な根拠でもある。
③ 特許クレームの解釈は、使用されている文言の厳密な文字通りの意味だけに依存するものではない。むしろ、明細書および図面は、特許クレームの曖昧さを解決するためだけでなく、常に特許クレームの解釈のための説明的な補助として使用しなければならない。
④ しかしながらこのことは、特許クレームがガイドラインとしてのみ機能すること、および、その主題が、明細書および図面の検討から、特許権者が期待したものにまで及ぶ可能性があること、を意味するものではない。
⑤ 特許クレームは、当業者の観点から解釈されるべきである。
⑥ これらの原則を適用するにあたっての目的は、特許権者に対する十分な保護と第三者に対する十分な法的確実性とを組み合わせることである。
⑦ 特許クレームの解釈に関するこれらの原則は、侵害の評価および欧州特許の有効性に等しく適用される。これは、EPCの下で特許クレームが、EPC第69条による特許の保護範囲を規定し、したがって、EPC第52条から第57条の特許性の条件[iv]を考慮して、EPC第64条[v]の下で指定締約国における特許権者の権利を規定する、という機能から生じる。
(2)SES-imagotag SA v. Hanshow Technology Co. Ltd., et al.事件
NanoString事件の控訴審判決に引き続いて、UPCの控訴裁判所は、2024年5月13日付けのSES-imagotag SA v. Hanshow Technology Co. Ltd., et al.事件の控訴審判決(UPC_CoA_1/2024)[vi]において、NanoString事件控訴審判決で採用された上述の原則を適用しました。この仮差止請求事件の控訴審判決において控訴裁判所は、本件特許の明細書を検討した結果、電子チップとアンテナとを電子ラベル上または電子ラベル内の異なる位置に配置できることは教示されていたものの、それらを同じ表面に配置することやアンテナを電子チップの隣の背面に配置することの欠点が開示されていると結論付けました。この結果、控訴裁判所は、クレームはプリント回路基板上の電子チップとアンテナとの間に空間的な分離を要求していると解釈し、その点において第一審裁判所の請求棄却の結論に同意しました。
2.UPC地方部でのクレーム解釈の原理に関する最近の判決例(Agfa NV v. Kering事件)
上記の控訴審判決以降、UPCの裁判官はこれらの控訴審判決を適用し、UPCにおいては明細書の内容がクレームの範囲を理解する上で決定的に重要であることを示してきました。以下に、このような状況下において下された近時のUPCハンブルク地方部の判決について紹介いたします。
(1)事件の経緯
Agfa NV(以下、「Agfa社」)は、装飾的な画像で天然皮革を装飾するための製造方法および装飾的な画像で装飾された天然皮革に関する欧州特許第3388490号(以下、「本件特許」)を所有しています。Agfa社は、Guccio Gucci S.p.aなどの欧州企業9社が製造販売しているバッグ、靴、カードケースなどの一連の高級コレクションに属する製品群が、本件特許を侵害しているとしてUPCのハンブルク地方部に特許侵害訴訟を提起しました。被告の9社はすべて、複数の高級ブランド(グッチ、サンローランなど)を擁するフランスの複合企業Kering傘下の欧州企業でしたので、ここでは被告企業9社を「Kering社」と総称します。侵害訴訟に対して被告Kering社は、本件特許の取消を求める反訴を提起しました。これにより、ハンブルク地方部での本件訴訟(Agfa NV v. Kering事件:UPC_CFI_278/2023)においては、本件特許の侵害および有効性が争われました。
(2)本件特許について
本件特許の発明は、クラスト処理された皮革(いわゆるクラストレザー)[vii]の上にある下地コーティングに、黒色とは異なる無彩色を使用し、その下地コーティング上にインクジェット印刷されたカラー画像を組み合わせることで、天然皮革に装飾的な画像を付与するものです。本件特許の争われたクレームのうちの代表的な独立クレームとして、クレーム1(原文および弊所仮訳による和訳)を以下に示します(特徴部分を太字・下線で示します)。
**********
A manufacturing method for decorating natural leather with a decorative image including the steps of:
– applying on a crusted leather (45) a base coat (44) containing a pigment for providing an achromatic colour different from black;
– inkjet printing a colour image (43) on the base coat (44) using one or more pigmented UV curable inkjet inks;
– optionally applying a protective top coat (42) on the image (43); and
– optionally applying a heat pressing or embossing step;
wherein the achromatic colour different from black of the base coat and the inkjet printed colour image are used in combination to provide the decorative image.
(装飾的な画像で天然皮革を装飾するための製造方法であって、
-黒色とは異なる無彩色を提供するための顔料を含む下地コーティング(44)を、クラスト処理された皮革(45)上に塗布する工程;
-1つまたは複数の着色されたUV硬化型インクジェットインクを用いて、下地コーティング(44)上にカラー画像(43)をインクジェット印刷する工程;
-必要に応じて、前記画像(43)上に保護用トップコーティング(42)を塗布する工程;および
-必要に応じて、熱プレスまたはエンボス加工の工程を適用する工程;
ここで、下地コーティングの黒色とは異なる無彩色とインクジェット印刷されたカラー画像とを組み合わせて用いて、装飾画像を付与する。)
**********
(3)事件の争点
本件訴訟における両当事者(原告Agfa社および被告Kering社)の主張は多岐に渡り広範なものであるため、本稿では、争点の核心部分についてのみ解説いたします(両当事者の主張の詳細については、本稿末尾に挙げた情報元②(判決原文)を参照ください)。
本件訴訟の争点の中心は、本件特許の独立クレーム、例えば上記のクレーム1において太字・下線で示した「黒色とは異なる無彩色を提供するための顔料を含む下地コーティング(a base coat containing a pigment for providing an achromatic colour different from black)」という特徴、特に「無彩色(achromatic colour)」という用語の定義であり、両当事者はこの「無彩色」という言葉の解釈について互いに同意しませんでした。より具体的には、この「無彩色」というクレーム用語が、「象牙色のような暖色系の白色(いわゆるオフホワイト、アイボリーホワイト等)」を含まない「完全な無彩色(白色)」を意味するものと限定的に解釈されるかどうかが争点となりました。
(4)争点に関する原告の主張
原告であるAgfa社は、被告Kering社が製造販売する革製品は高級品と認識されており、そこでは象牙色のような暖色系の白色は純白よりも好まれることを指摘しました。そして、原告は、白色には象牙色を含む多くの色合いがあり、本件特許における無彩色たる白色は象牙色を含む多様な色合いを含むとものと解釈されるべきであること、被告製品で用いられるような象牙色は、クレーム1に記載された「黒色とは異なる無彩色」に相当すること、を主張しました。
より具体的に、原告は、二酸化チタンのような白い顔料を用いることによって無彩色を得ることができるが、下地コーティングの色をわずかに変化させるために追加の顔料を加えることによってもなお無彩色を得ることができると主張しました。特に原告は、大量の無彩色の顔料に少量の有彩色の顔料を加えてもなお無彩色の下地コーティングを得ることができる、と主張しました。原告は、本件特許の明細書の段落[0021]および実施例3に依拠して、本件特許は「完全な」無彩色または無彩色から識別不能なほどわずかに変化した色相のみの保護を求めているのではなく、むしろ、少量の有彩色顔料を含み、オフホワイトまたはアイボリーホワイトの色を有する下地コーティングの保護も求めている、と主張しました。原告が依拠した本件特許の明細書の段落[0021]は、「有彩色」および「無彩色」について以下のように述べています。
**********
A chromatic colour is any colour in which one particular wavelength or hue predominates. For example, blue and green are chromatic colours, while white, grey, and black are achromatic colours, as they have no dominant hue, meaning that all wavelengths are present in approximately equal amounts within those colours.
(有彩色とは、1つの特定の波長または色相[viii]が優勢な色である。例えば、青色と緑色は有彩色であるが、白色、灰色、黒色は優勢な色相を持たず、これらの色にはすべての波長がほぼ同量で存在するため、無彩色である。)
**********
(5)争点に関する被告の主張
被告であるKering社は、上記の段落[0021]について、ある色が平坦なスペクトル応答[ix]を有する場合に、またはスペクトル応答が完全に平坦でなくても、完全に平坦なスペクトルからの偏差が、その色と完全に平坦なスペクトル線を有する最も近い無彩色の基準色との違いが平均的な観察者に知覚されない程度でのものある場合に、その色が本件特許の意味するところにおいて無彩色であることを教示するものであると解釈しました。被告によれば、段落[0021]における「ほぼ同量(approximately equal amounts)」とは、人間の目が最も近い「完全な」無彩色との差を知覚できない限り、その色は無彩色であることを意味し、最も近い完全な無彩色とは、すべての波長が同じ反射強度を持つ色を指します。
被告はさらに、本件特許の明細書の段落[0026]および[0027]で説明されているΔE94指標について言及しました。ここで、ΔEは「色の違いの度合いを示す尺度」である色差を表す指標であり、その値が0であれば全く同じ色、数値が大きくなるほど違いが大きいことを意味します。本件訴訟で言及されるΔE94とは、国際照明委員会が1994年に定めた色差を表す数値式の改訂版を意味し、ΔE94指標とは、ΔE94の数値式を基準として色の違いを測定する枠組みを言います。段落[0026]によれば、着色されたクラスト処理された皮革の表面とインクジェット印刷されたカラー画像の対応部分との間の色の違いはΔE94指標を用いて最小化されます。段落[0027]によれば、ΔE94指標が10.0よりも小さければ2つの色は類似であることが記載されています(ただし、ΔE94指標が1.0よりも小さければ、人間の目では色の違いを知覚することはできません)。被告が指摘するように、ΔE94指標は、人間の目が色の違いをどのように知覚するかを決定するために使用できる指標であり、被告によれば、当業者は、すべての波長がほぼ同量存在しているため平均的な観察者には色差が知覚できないかどうかを判断できる客観的かつ再現可能な基準が必要であることを理解しています。被告は、このような基準が必要であるという問題は、無彩色および有彩色の境界線を判断するためにΔE94指標を使用するという選択肢に自動的に当業者を導くであろうと主張しました。
(6)裁判所の判断
ハンブルク地方部はまず、クレームの「黒色とは異なる無彩色を提供するための顔料を含む下地コーティング」という記載において「無彩色」という用語が顔料(pigment)を指すのか、それとも下地コーティング(base coat)全体を指すのかを検討しました。前者の解釈、すなわち顔料のみが無彩色である必要がある場合、下地コーティングはその一部に、黒とは異なる無彩色の顔料を含むことができますが、後者の解釈では、下地コーティング全体が黒とは異なる無彩色であることが求められます。ハンブルク地方部は、クレームの最終段落の特徴が「下地コーティングの黒色とは異なる無彩色(the achromatic colour different from black of the base coat)」と述べていることから、クレーム全体を考慮すると後者の解釈が正しいと判断しました。
ハンブルク地方部は、NanoString事件において確立された原則、すなわち特許はクレームされた特徴の定義に関して「独自の辞書」として使用できることを認めつつも、これは明細書のうちで争点となっている特徴に関連する部分に限定されることを明確にしました。特に本件訴訟においては、争点に関連して、人間の目が色をどのように認識するかを理解するための指標であるΔE94指標についての明細書の記載が議論されました。ハンブルク地方部の見解では、ΔE94指標に関する議論は、染色されたクラスト処理された皮革の色を復元することに関するものであり、本件で争点となっているクラスト処理された皮革に塗布される下地コーティングの顔料に関連して特許のクレームで使用されている「無彩色」という用語の定義に関する特許の教示内容には含まれませんでした。
より具体的に、ハンブルク地方部は、このΔE94指標に関する問題は段落[0021]に示されている「無彩色」の定義とは実際には無関係であると考えました。ΔE94指標は、必要に応じて白色の下地コーティングに背景色と同様の色をインクジェット印刷することにより、染色されたクラストレザーの色を復元しようとする場合に導入されるものです。この実施形態では、染色されたクラスト処理された皮革の表面の色と、インクジェット印刷されたカラー画像内の対応する部分の色との間の色差が、ΔE94指標を基準として最小化されることが説明されており、前述のように、ΔE94指標が10.0よりも小さければ2つの色は類似であることが明細書に記載されています。このように、明細書においては、色の「類似」の概念に適用される基準としてΔE94が定義されています。このことから、ハンブルク地方部は、2つの色の違い(類似するか否か)と、無彩色および有彩色の境界線とは、全く異なる概念である点を指摘しました。このように、明細書におけるΔE94指標に関する議論は、争点となっている特徴、すなわち無彩色および有彩色の境界線に関連するものではありません。
実際、灰色は白色とは異なる色ですが、どちらも無彩色です。無彩色の定義について、段落[0021]に示されている定義、すなわち、支配的な色相を持たず、すべての波長がほぼ同量でその色内に存在する色という定義から逸脱する理由はありません。白色は典型的な例です。この解釈によれば、波長の分布に偏りがある象牙色の下地コーティングは特許の白色の範囲に含まれません。
原告であるAgfa社は、白色には象牙色を含め多くの色合いがあり、特許における「白色」はこれらの色合いを含むと解釈されるべきであると主張しました。しかし、ハンブルク地方部は、クレームは「無彩色」に言及しており、明細書では白色が無彩色の例として示されているものの、すべての色合いの白色が特許における無彩色の定義に該当するわけではないと指摘しました。ハンブルク地方部は、原告によるこのクレームの特徴の解釈は過度に広範であり、特許によって裏付けられていないと判断しました。
ハンブルク地方部は、「無彩色」という用語の解釈に関してこのような結論に至り、2025年4月30日付の判決において、特許侵害の訴えを棄却しました。同時に、ハンブルク地方部は、引用された先行技術文献のそれぞれに対して特許が新規であるとして特許取消の反訴も棄却しました。
(7)考察
UPCにおいて、明細書の内容は、クレームの範囲を理解する上で決定的に重要です。NanoString事件でUPC控訴裁判所が示した原則を適用したUPC地方部の先行するいくつかの判決[x]では、明細書に提示されたすべての実施形態が解決不可能な矛盾を生じないという条件で、または本発明に従う実施形態ではないことが明示的に示されている場合を除いて、クレームは、クレームされた発明の部分を構成するものとして明細書に提示されたすべての実施形態を含むように解釈されるべきであるとされています。しかし、これらの判決はいずれも、明細書によって裏付けられている範囲を超えるクレームの広さの解釈は認められないことを示しています。したがって、クレームは、特許で考慮されていない実施形態を含むように広く拡張することなく、明細書に提示されたすべての実施形態を含むように解釈されるべきです。
[担当]深見特許事務所 堀井 豊
情報元①Claim interpretation: more clarity on claim construction at the UPC
(https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-claim-interpretation-construction)
情報元②(Agfa NV v. Kering事件判決原文)
[i] この控訴審判決の概要については、弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2024年5月8日付け配信記事「UPC控訴裁判所による最初の実体的判決」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/11384/)をご参照ください(ただし、特許の有効性に関する争点のみに焦点を当てて解説)。
[ii] EPC第69条第1項は「保護の範囲」に関して以下のように規定しています。
(1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は,クレームによって決定される。ただし,明細書及び図面は,クレームを解釈するために用いられる。
[iii] 各国の裁判所は独自の解釈手法を採用しEPC第69条第1項の解釈をめぐっても見解が分かれたため、権利解釈のさらなる統一を図るべく、EPCでは、第69条の解釈に関する議定書(プロトコル)を採択し、妥協点を図りました。EPC第69条のプロトコールは次のように規定します:
第69条は、欧州特許によって与えられる保護が、クレームに使用されている文言の厳格な文言上の意味によって定められると理解されるものとして解釈すべきではなく、また、明細書および図面が、クレーム中に見られるいずれかの不明瞭さを解決するという目的のみで使用されるものと解釈すべきでもない。
更に、第69条は、クレームが指針としてのみ供されるものとして解釈すべきでもなく、また、欧州特許によって与えられる実際の保護が、当業者が明細書および図面を考慮する範囲内から、特許権者が意図していた範囲にまで及ぶ可能性があるという意味にも解釈されるべきではない。
反対に、第69条は、これらの両極の間にある、特許権者に対する公正な保護と、第三者に対する合理的な程度の確実さとを組合わせた位置を定めているものとして解釈されるべきである。
[iv] EPCの第52条~第57条は特許要件を定めた条項です。第52条は「特許可能な発明」、第53条は「特許性に対する例外」、第54条は「新規性」、第55条は「新規性を喪失させない開示」、第56条は「進歩性」、第57条は「産業上の利用」について規定しています(条文の内容については特許庁ホームページを参照ください(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf))。
[v] EPC第64条は、EPCによって与えられる権利について以下のように規定しています。
(1) 欧州特許は,(2)の規定を条件として,その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
(2) 欧州特許の対象が方法である場合は,特許によって与えられる保護は,その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。
(3) 欧州特許権の侵害は,すべて国内法令によって処理される。
[vi] この控訴審判決の概要については、弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2024年8月5日付け配信記事「UPC控訴裁判所がクレーム解釈の原則を示した仮差止請求事件の控訴審判決」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/12006/)をご参照ください。
[vii] クラスト処理とは、革の鞣し(なめし)から仕上げ前までの中間的な工程を含む処理をさす言葉。
[viii] 「色相」とは、「色の三属性(明度、彩度、色相)の一つであって、赤、青、緑などの色の人間が感じる色味、色合い」を言い、必ずしも単一の波長に対応せず、特定の波長を中心として所定の幅に分布します。段落[0021]における「色相」はこのような特定の波長を中心として所定の幅に分布する色合いを指すものと解されます。
[ix] 光のスペクトルとは光の波長の強度分布を意味するものであり、「スペクトル応答」とは、「物体が異なる波長の光をどのように反射、吸収するかという光の波長ごとの反応特性」を意味すると解されます。特に、本件訴訟で言及される「平坦なスペクトル応答」とは、すべての波長の光に対してほぼ同じ強さで反応(例えば反射)する特性を指すものと解されます。
[x] UPC_CFI_373/2023およびUPC_CFI_252/2023