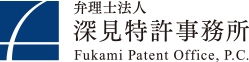先願のクレーム発明は後願の出願人の発明に由来しないとして冒認を認めなかったPTABの決定を支持したCAFC判決
米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、米国特許法の改正法である米国発明法(America Invents Act:AIA)で導入された冒認手続(derivation proceeding)[i]に関する最初の判決を下し、先願のクレームに係る発明は後願の出願人の発明に由来しない独自の発明であって冒認はなかったとする米国特許庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)の判断を支持しました。
Global Health Solutions, LLC v. Marc Selner, Case No. 2023-2009 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025) (Stoll, Stark, JJ.) (Goldberg, J., sitting by designation)
1.事件の背景:冒認手続制度の導入
(1)AIAの成立:先発明主義から先願主義への転換
2011年9月16日にAIAが成立し、2013年3月16日に施行されました。AIAは、米国特許制度を先発明主義から先願主義へと転換することにより、同一発明に関する出願が競合する場合にいずれを優先するかを決める方法を変更しました。
AIA施行以前は、最初の発明者は、たとえ同じ発明についての二番目の発明者が先に出願したとしても、自分が最初の発明者であることを証明できれば特許を取得することができました。そして発明日の先後を争うための手続として、抵触審査手続(interference procedure:以下、「インターフェアレンス」)の制度が設けられていました(AIA改正前の旧特許法135条)。これが、米国における従来の「先発明主義」制度の本質でした。
(2)インターフェアレンスの概要
旧法のインターフェアレンスの手続は、異なる出願人が、実質的に同一の発明をクレームしたそれぞれの特許出願をしている場合に、どちらが先に発明を完成したかをUSPTOの特許審判インターフェアレンス部(Board of Patent Appeals and Interferences)が審査する手続であり、特許出願と特許出願との間、または特許出願と特許との間で行われます。それぞれの出願の有効出願日に基づき後願者に先発明の立証責任が課せられます。
発明完成の優先順位は基本的に、①発明を着想した日(date of conception)、②発明を実施化した日(date of reduction to practice)、③発明者が発明を実施化することについていかに熱心であったか(diligence)、に基づいて決定されます。[ii]
(3)AIA下の冒認手続
AIA改正前の旧法とは対照的に、AIA下の新法では、二番目の発明者が先に出願した場合、最初の発明者は原則として特許を受ける権利を有しません。これは、「先願主義」制度への移行によるものです。
しかしながら、AIAは、二番目の発明者が先に出願したにもかかわらず、最初の発明者である二番目の出願人が特許を取得できる限られた機会を残しています。それは、最初の出願人の発明が二番目の出願人の発明に由来する場合です。すなわち、最初の発明者である二番目の出願人は、自分が発明を着想しかつ自身の特許出願をする前にその発明が最初の出願人に伝わったことを証明しようと試みることができます。AIAは、最初の発明者である二番目の出願人が、PTABにおける冒認手続において最初の出願人に対してそのような請求をすることを認めています(AIA改正後の新特許法135条)。本稿では、PTABで争われた冒認手続の結論についてCAFCが初めて判断を下した事件について報告するものです。
2.事件の経緯
(1)冒認手続の請願
Global Health Solutions LLC(以下、「GHS社」)およびMarc Selner氏(以下、「Selner氏」)はそれぞれ、AIAの施行後(2013年3月16日以降)に、創傷治療用軟膏に関する同じ発明(以下、「本件発明」)を対象とする特許出願を行いました。より具体的に、Selner氏は、2017年8月4日に自身を単独の発明者とする米国特許出願番号15/549,111(以下、「’111出願」)を出願し、GHS社はその4日後の2017年8月8日に、その創業者であるBradley Burnam氏(以下、「Burnam氏」)を単独の発明者とする米国特許出願番号15/672,197(以下、「’197出願」)を出願しました。
本件発明がなされた当時、先願者であるSelner氏は、Burnam氏とプロジェクトを共同実施するなど協力関係にありました。GHS社は、Selner氏の’111出願の存在を知って、Selner氏は’111出願を先に提出しているが真の発明者ではなく、そのクレーム発明は、’197出願の単独発明者であるBurnam氏の発明に由来すると主張して、Selner氏に対する冒認手続の請願をUSPTOに提出いたしました。
(2)PTABの審理
PTABの審理において、Selner氏は自身のクレーム発明はBurnam氏の発明に由来するものではなく独立して発明したものであると主張しました。両当事者は、複数の電子メールによるやり取りを含む、クレームされた発明のそれぞれの着想時期に関する証拠を提出しました。これらの証拠(電子メールの送受信記録)に基づいて、PTABは、Burnam氏が発明を着想し、それを2014年2月14日午後4時4分までに電子メールを通じてSelner氏に伝達したことをGHS社が証明したと認定しました。一方、PTABは、Selner氏とBurnam氏との間で交わされた別の電子メールにより、Selner氏が同日のさらに早い時刻である午後12時55分までに発明を着想していたことをSelner氏が証明したと認定しました。
このようにPTABは、電子メールの送受信記録から、Burnam氏が発明内容をSelner氏に伝えるよりも早くSelner氏が本件発明を着想していたと認定し、Selner氏が最先の発明者であって、そのクレーム発明をBurnam氏から引き出したことはあり得ないと判断しました。また、GHS社は、クレームされた発明の着想を完成するには現実の実施化が必要であったと主張しましたが、PTABは、このようなGHS社の主張を却下しました。GHS社はこの決定を不服としてCAFCに上訴しました。
3.CAFCの審理
CAFCは、AIA改正前のインターフェアレンス手続とAIA改正後の冒認手続との相違に関して、PTABの判断には、AIA改正前のインターフェアレンス手続と同じ様に、どちらが先に発明したかという先発明主義的な分析に焦点を当てたことに誤りがあったことを指摘しましたが、そのような誤りは無害であったと判断し、結論においてはPTABの決定内容を支持しました。
CAFCは、AIAは冒認手続の請願のための証拠要件を明確に定義していないと指摘し、旧法下のインターフェアレンスにおける判例法を参考的に援用しました。冒認の申立に関する既存の判例はしばしば、AIA改正前の先発明主義の下で誰が発明の優先権を有するかを判断するために用いられ、AIA改正後には適用されなくなったインターフェアレンス手続に関連して提示されることがあります。インターフェアレンス手続は、どちらの当事者が発明対象を最初に発明したかを判断することに焦点を当てています。たとえば、CAFCの先例(Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d 1321, 1332(Fed. Cir. 1998))は、「インターフェアレンス手続きにおいて冒認を証明するには、冒認を主張する当事者は、クレームされた主題を先行して着想したことと、その着想を相手方に伝達したこととを立証する必要がある」と判示しています。
CAFCは、AIA下の冒認手続においても、旧法下のインターフェアレンスと同様に、クレームされた発明の着想と伝達の両方の立証が必要であると判断しました。AIA下における冒認手続でも、請願人(後願側)に優越的証拠(preponderance of the evidence)を証拠基準とする立証責任(burden of proof)が課せられます。その一方で、CAFCは、AIA以前のインターフェアレンス手続における判例で明示された基準は、AIA独自の法的枠組みに照らして慎重に適用されなければならないことを強調しました。
CAFCは、PTABがどちらの当事者が最先の着想の証拠を有していたかという、典型的なインターフェアレンス手続における決定的争点に焦点を当てていたものの、それは無害な誤りであったと判断しました。AIA下の先願主義の枠組みでは、先発明者の決定は決定的な争点ではありません。CAFCは、Selner氏が先に出願したため、自身の着想がBurnam氏の着想とは独立していることを示すだけで十分であると指摘しました。本件では、Selner氏がより早く着想した証拠はまた、Selner氏の着想がBurnam氏とは独立したものであることの証拠でもあったとCAFCは指摘しました。
CAFCはまた、Selner氏が現実の実施化の証拠がないため発明を立証できなかったというGHS社の主張をPTABが却下したことは誤りではなかったと判断しました。CAFCは、PTABが、複雑で予測不可能な技術に対してインターフェアレンス手続においてしばしば適用されるこのような要件が本件発明に適用されるかどうかについて、適切に検討したと判断しました。CAFCは、Selner氏の着想は、発明をその製造方法によって定義できた時点または完全で有効な発明であるという明確かつ永続的なアイデアを形成した時点のいずれかで、完成したと説明しました。Selner氏がBurnam氏に送った先の電子メールのやり取りは、Selner氏が実際の実施化を必要とせずに完全な着想を確立するために必要な理解に達していたという認定を裏付けています。
CAFCは、PTABが誰が最初に発明したかに焦点を当てたことは誤りであったものの、Selner氏がBurnam氏からの伝達前に独立して着想したという事実認定は有効であるとして、Selner氏に有利なPTABの決定を支持し、冒認性はないと判断しました。
4.実務上の注意点
本件は、AIA下における冒認手続とAIA以前のインターフェアレンスの分析との根本的な違いを浮き彫りにしています。旧法のインターフェアレンスでは誰が最初に発明をしたかが問題になりますが、AIA下の冒認手続においては、誰が最初に発明したかが問題ではなく、単に自身の発明が独自になされたことを証明すれば足ります。すなわち、最初の出願人(本件のSelner氏)がその発明を冒認手続の請願人(本件のBurnam氏)から実際に引き出したのか否かを、請願人が先にその発明を最初の出願人へ伝えたか否かに基づいて立証できるかどうかが焦点となります。したがいまして、本件で証拠として威力を発揮した電子メールの送受信記録など、後日の紛争に備えて重要な証拠資料は確実に保存しておく必要性が理解されます。
[i] “derivation proceeding”の訳語としては、「冒認手続」、「由来手続」、「派生手続」等が一般的に使用されていますが、ここでは「冒認手続」を使用することといたします。
[ii] インターフェアレンスの審査では、たとえば、一方の出願人の方が、発明を着想した日および発明を実施化した日の双方が他方の出願人より早いときには、当該一方の出願人に特許を受ける権利が認められます。また、一方の出願人の方が、他方の出願人より発明を着想した日が早かったものの発明を実施化した日が後になった場合には、一方の出願人は、発明の着想から実施化に至る期間に発明を実施化するために熱心な努力をした場合に限り特許を受ける権利が認められます。
[情報元]
1. McDermott Will & Emery IP Update | September 11, 2025 “Derivation proceedings highlight race to file under AIA“
(https://www.ipupdate.com/2025/09/derivation-proceedings-highlight-race-to-file-under-aia/)
2. Global Health Solutions, LLC v. Marc Selner, Case No. 2023-2009 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025) (Stoll, Stark, JJ.) (Goldberg, J., sitting by designation)(判決原文)
(https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2009.OPINION.8-26-2025_2563662.pdf)
3. Global Health Solutions, LLC v. Marc Selner, Case No. 2023-2009 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025) (Stoll, Stark, JJ.) (Goldberg, J., sitting by designation)(判決原文)
(https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2009.OPINION.8-26-2025_2563662.pdf)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊