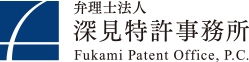付託G1/24に関する拡大審判部の決定
欧州特許庁(EPO)においては、最上級の審判機関である拡大審判部が、クレーム解釈に際して明細書を参照すべきかどうかについての審判部からの付託G1/24に対する判断を示しました。本稿では拡大審判部の決定の内容を分析し、すべての未解決の問題が解決されたかどうかを検討します。
1.付託G1/24が出された背景
特許の範囲を決定することは、当該特許の侵害および有効性の両方の判断にとって重要です。特に、特許は新規で創造性のある対象物に対してのみ付与されるべきです。そのため、欧州特許庁(EPO)での特許付与手続きおよび異議申立手続きの両方において、特許出願または特許のクレームがカバーする範囲については必然的に問題となります。
この点に関する基本的な問題は、特許明細書の記載が特許の保護範囲にどの程度影響を与えるかということです。例えば、明細書の記載にはクレームの用語の狭義の定義が含まれている場合がありますが、その用語は当業者にとってより広い意味を持つことがあります。この場合の問題は、その定義をクレームに読み込むことで、保護範囲を狭めるべきかどうかです。あるいは、明細書の記載によって、クレームの文言だけに基づいた場合よりも広い解釈が導かれることもあります。さらに、明細書の記載中の説明を、特定の状況下でのみ考慮すべきかどうかという問題もあります。
これらの問題に関するEPOの判例法が分かれている中で、EPO審判部は、欧州特許EP 3076804 B1(以下「本件特許」)を審査段階で付与されたとおりに維持するというEPO異議部の決定に対する審判T0439/22(技術審判部3.2.01が担当)の2024年6月24日付け中間決定において、拡大審判部に対してクレーム解釈に関する質問を付託(G1/24)しました。以下、審判T0439/22を担当した技術審判部3.2.01を「付託審判部」とします。
本件特許は、エアロゾル形成材料であるタバコを含む電子喫煙装置用部品に関しており、審判T0439/22における主要な争点は、特許クレーム1が新規性を有するかどうかでした。特許クレーム1には、「集束シート(gathered sheet)」という特徴が含まれており、特許権者(審判被請求人)は、「集束シート」という語句が当業者における通常の意味に従って解釈されるのであれば、クレーム1は新規性を有すると主張しました。一方異議申立人(審判請求人)は、「集束シート」を明細書の記載に照らして解釈すれば、技術的に合理的なより広い意味を持つことになると主張しました。その場合、特許クレーム1は新規性を欠くことになります。
2.付託の内容
付託審判部により付託された法的問題は、特許出願の審査中のクレームの解釈に関するものであり、付託における質問の内容は以下の通りです。
[質問1]審査段階において、特許要件を規定するEPC52条~57条に基づいて発明の特許性を評価する際の特許クレームの解釈にも、EPC69条(1)[i]およびその解釈に関する議定書の1条[ii]が適用されるべきかどうか。
[質問2]特許性を評価するためにクレームを解釈する際に、明細書と図を参照できるかどうか。もしそうなら、これは一般的に行われるか、あるいは、クレームが単独で読まれたときにクレームが不明瞭または曖昧であると判断した場合にのみ行なうことができるのか。
[質問3]クレームにおける用語の定義が明細書に明示的に示されている場合、特許性を評価するためにクレームを解釈する際に、この定義を無視することができるかどうか。もしそうなら、どのような条件下でその定義を無視できるのか。
審判T0439/22の2024年6月24日付け中間決定の内容については、弊所HPの「国・地域別IP情報」において2024年9月13日付で配信した「クレーム解釈に関する拡大審判部への付託G1/24、ならびに 審査および異議申立手続の継続に関する欧州特許庁からの通知」と題した欧州関連記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/12237/)をご参照下さい。
3.付託審判部の見解
付託審判部は、係争中の審判事件において特許クレームをどのように解釈すべきかの問題に関して、判例が異なる見解に分岐しているとの見解を示しました。
質問1に関して付託審判部は、判例が2つの異なる法理の系列を有することを特定しました。そのうちの一方の系列は、EPC第52条から第57条に基づく発明の特許性を評価する際に、特許クレームの解釈の法的根拠としてEPC第69条および議定書第1条に求めるものです。もう一方の系列は、EPC第84条[iii]を基礎とするものです。また、EPC第52条から第57条に基づく発明の特許性を評価する際に、EPCのどの条項が特許クレームの解釈の法的根拠であるかについて明確にされていない判例系列も存在するとの見解を示しました。
質問2に関して付託審判部は、判例の2つの対立する判例系列があることを確認しました。そのうちの1つの判例系列は、審判部が特許性評価のためにクレームを解釈する際に、当業者がクレームを単独で読んだ場合にクレームが不明確または曖昧であると判断したときに、審判部が特許の明細書および図面を参照するというものでした。もう1つの判例系列は、特許性を評価するためにクレームを解釈する際に、審判部が常に明細書および図面を参照するというものでした。
4.拡大審判部における審理
(1)提出された書面および口頭審理
特許権者、異議申立人、およびEPO長官は、付託された質問を拡大審判部に提出しました。さらに拡大審判部には、30件を超えるアミカスブリーフ(第三者意見書)が提出されました。
また、2025年3月28日に口頭審理が開催され、特許権者、異議申立人、およびEPO長官の代理人が出席しました。口頭手続きの終わりに、拡大審判部の責任者は、拡大審判部がやがて書面で決定を下すと発表しました。
(2)付託の受理可能性(Admissibility)について
拡大審判部は、質問3が質問2に包含されていると判断し、質問2に答える予定である以上、質問3への回答は付託審判部が事件を解決する上で必要ではないため、質問3は不受理とされました。
質問1および2については、判例が異なる判断を示しており、また、重要な法律問題に関わることから、拡大審判部は、これらの質問については受理可能であると判断しました。
(3)質問1および2の審理
(i)クレーム解釈の必要性と、クレーム解釈実行のための法的根拠の候補について
EPC第52条から第57条に基づく発明の特許性を評価する際に、EPOの各部門がクレームを解釈する必要があることは、議論の余地がありません。
質問1の趣旨は、この解釈を実行するためのEPCの法的根拠をどこに求めるかという点にあり、その法的根拠の候補として、次の2つの立場が考えられます。
立場A:EPC第69条およびその解釈に関する議定書を根拠とする立場
立場B:EPC第84条を根拠とする立場
過去の拡大審判部のいくつかの決定でもこの問題に触れられていますが、いずれも決定的な争点ではありませんでした。今回の決定に際して拡大審判部は、立場AおよびBのいずれも、特許性を評価する際のクレーム解釈の基礎として完全に満足できるものではないと考えました。その理由は以下の通りです。
EPC第69条はEPC第III章「欧州特許と欧州特許出願の効力」に記載されており、本来、国内裁判所とUPCでの侵害訴訟にのみ関係しています。このような結論は、EPC第69条と議定書の文言や、これらの規定の起草履歴からも導き出すことができます。
クレームの解釈の根拠としてEPC第84条を使用することも、批判される可能性があります。EPC第84条は特許出願の内容を扱っており、本質的に形式的なものを対象としており、発明については言及せず、クレームの解釈方法に関するガイダンスも提供するものでもありません。クレームに何を含める必要があるかを起草者に指示し、クレームがその目的を満たしているかどうかを判断するためのEPOへの指示を定めているだけです。
したがって、拡大審判部は、特許性を評価する際のクレーム解釈には、EPCの条項に関して明確な法的根拠がないと考えています。上記を考慮すると、質問1に対する厳密に正式な答えは「いいえ」になります。
(ii)付託G1/24の決定において詳細に検討された判例から導かれる実質的原則
付託G1/24の決定において拡大審判部は、過去の審判部の決定(T2684/17,T1871/09,T1473/19等)を詳細に検討し、これらの審判例に基づいて、以下の2つの原則を抽出しました。
[原則1]クレームが特許性判断の出発点および基礎となる。
の許の明細書および図面を参照する。
(iii)過去の判例において分岐していた判断の整理
上記原則1については、すでに確立しています。しかしながら上記原則2を導くに際しては、これまでの審判部の判例で判断が以下の2派に分岐しており、この分岐が質問2の争点となっていました。
A派:クレームの記載が不明確な場合のみ明細書および図面を参照する。
B派:クレームの記載が不明確な場合に限らず、常に明細書および図面を参照する。
拡大審判部は、上記A派を否定し、B派に基づいて上記原則2を採用しました。その理由は次の通りです。
(イ)A派の立場は、EPC第69条には「クレームが不明確な場合にのみ明細書を参照する」とは明記していないため、同条の文言およびその解釈に関する議定書と整合しない。
(ロ)A派の立場は加盟国裁判所やUPCの実務と乖離していることから、それらと整合させる必要がある。
(ハ)クレームの記載が明確か否かを判断する行為自体が既に解釈行為であり、解釈の前段階に不明確性の有無を置くのは非論理的である。
(iv)質問2についての拡大審判部の回答
上記判断に基づき、拡大審判部は、質問2について、「明細書および図面は、クレームの記載が不明確さや曖昧さを含む場合だけでなく、クレームを解釈する際に常に参照される。」と回答しました。
拡大審判部は、2024年2月26日のUPC控訴裁判所のNanoString Technologies v. 10x Genomicsの命令 の“HEADNOTES”の項目「2」の記載を引用して、UPCの現在の判例法は、上記の結論と一致しているという点に言及しています。NanoString Technologies v. 10x Genomics事件のUPC控訴裁判所判決については、弊所HPの「国・地域別IP情報」において、2024年8月5日に「UPC控訴裁判所がクレーム解釈の原則を示した仮差止請求事件の控訴審判決」と題して配信した欧州関連記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/12006/)、および2025年9月18日に「UPCにおけるクレーム解釈の原則に関する最近の判決紹介」と題して配信した欧州関連記事において言及しておりますので、ご参照下さい。
また拡大審判部は、さらなる指針として、「クレームの不明確さに対する正しい対応は補正であり、解釈ではない」と述べて、曖昧なクレームを解釈で補うのではなく、EPC第84条に基づいて、補正により明確化すべきであることを表明しました。この点については、EPO長官のコメントにおいても強調されました。
(v)拡大審判部の命令
上記を踏まえて拡大審判部は、質問1および2に対する回答として、以下の命令を発出しました。
「[命令(Order)]クレームは、EPC第52条から第57条に基づく発明の特許性を評価するための出発点であり、基礎である。明細書および図面は、EPC第52条から第57条に基づく発明の特許性を評価する際に、当業者がクレームを単独で読んだときに不明確または曖昧であると判断した場合だけでなく、クレームを解釈するために常に参照されなければならない。」
5.今回の付託回答において未解決または留保された事項
付託G1/24に対する決定では、以下の事項が未解決または留保されています。
(1)特許明細書における定義の拘束力
付託G1/24に対する拡大審判部の決定では、付託の質問3を不受理としたため、「明細書に明示された定義をクレーム解釈において無視できる条件」については判断されませんでした。
(2)クレーム優位の原則の適用範囲
拡大審判部は、「クレームは出発点である」としつつ、常に明細書の記載を参照すべきであるとしたため、従来の「クレームの文言が最も優先される(primacy of claims)」という原則がどこまで維持されるかについては明示していません。言い換えれば、「クレームの文言優先」と「常に明細書を参照する」とのどちを重視するのかについては、今後の調整の余地が残されています。
(3)明細書の補正の法的根拠と範囲
拡大審判部は付託G1/24についての決定においては、「クレームの補正後に明細書をどの程度補正すべきか」については言及していません。クレームと明細書の整合性の問題については、別の審判事件T697/22の2025年7月付中間判決において拡大審判部への付託G1/25[iv]が出されていることから、G1/24の決定ではこの問題の判断を留保し、その法的根拠の判断も含めて付託G1/25についての決定に委ねられているものと思われます。
(4)明細書参照の程度について
拡大審判部は「常に明細書を参照すべきである」としましたが、どの程度まで(明細書全体の内容か、あるいは特定の関連部分など)参照すべきかについては明示していません。
6.実務上の留意点
付託G1/24に対する拡大審判部の決定を考慮して、実務上以下の点に留意すべきことが伺えます。
(1)拡大審判部がクレーム解釈の際に「明細書および図面を常にい参照すべきである」と明言した結果、EPOの審査官や審判官はクレームを読む際に明細書および図面を参酌する義務を負うことになることから、特許出願人側としても、明細書全体の記載がクレームと整合していることを事前に十分確認することの必要性が高くなります。
(2)付託における質問3が不受理になったことから、クレーム解釈に際して明細書中の定義をどこまで取り込むべきかは示されませんでした。よって、審査や訴訟において明細書に記載された用語の定義等を軽視あるいは無視できる範囲が依然不明確のままであることに留意すべきです。
(3)クレーム補正後の明細書の記載適合義務に関しては、今回の付託G1/24についての決定では言及しておらず、この問題については、EPOがそのウェブサイトで2025年8月5日に表明(https://www.epo.org/en/news-events/news/referral-g125-adaptation-description)しているように、付託G1/25についての拡大審判部の決定が出るまで、現行の審査ガイドラインに従う必要があることに留意すべきです。
[i] EPC69条(保護の範囲)の(1)は次のように規定しています。
「(1)欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は,クレームによって決定される。ただし,明細書及び図面は,クレームを解釈するために用いられる。」
[ii] EPC69条の解釈に関する議定書1条は、概ね次の事項を規定しています。
「第69条は、欧州特許によって付与される保護の範囲が、クレームに用いられた文言の厳密で文字通りの意味によって定義されるものと理解されるべきでなく、
その説明と図面は、クレームに見られる曖昧さを解決するためだけに使用されていることを意味すると解釈されるべきではない。
また、クレームがガイドラインとしてのみ機能すると解釈されるべきではなく、
付与された実際の保護が、当業者による明細書および図面の検討から、特許権者が考えていたものにまで及ぶ可能性があることを意味するものと解釈されるべきではない。
むしろ、特許権者に対する公正な保護と第三者に対する合理的な法的確実性を組み合わせた、これらの両極端の間の位置を定義するものと解釈されるべきである。」
[iii] EPC第84条(クレーム)は、次のように規定しています。「クレームには,保護が求められている事項を明示する。クレームは,明確かつ簡潔に記載し,明細書により裏付けがされているものとする。」
[iv] 付託G1/25については、弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2025年11月11日付け配信記事「明細書を補正クレームに適合させる必要があるか否かに関する質問をEPO拡大審判部に付託したEPO審判部の中間審決」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/14799/)をご参照ください。
[情報元]
1.Hoffmann Eitle Quarterly September 2025 “Roma Locuta, Causa Finita? The Implications of G 1/24 on Claim Interpretation”
https://www.hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2025-09.pdf#page=15
2.EPOホームページより
(1)G 0001/24 (The description and any drawings are always referred to when interpreting the claims, and not just in the case of unclarity or ambiguity.) 18-06-2025(拡大審判部の決定原文)
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ex1
(2)Press Communiqué of 18 June 2025 concerning decision G 1/24 (“Heated aerosol”) of the Enlarged Board of Appeal(拡大審判部の決定に関するPress Communiqué)
[担当]深見特許事務所 野田 久登