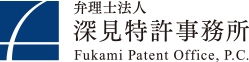韓国における最近の知的財産権保護強化のための、規則等改正および手続き効率化の取組について
2025年4月4日の弊所ホームページでの韓国関連の配信において、2024年11月以降に行なわれた韓国における特許等に関する規則や運用、法律の改正について紹介しました。その後も、韓国特許庁では、特許等の権利保護強化や知的財産関連手続きの効率化のための種々の取組がなされていますので、前回配信(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/13324/)の続報として、その主な取組内容を紹介します。
1.特許審判院、審判–調停連携制度活性化本格推進
(1)「審判–調停連携制度」の利用活性化の発表
韓国特許庁の特許審判院は2025年3月に、特許審判段階で当事者間の合意を通して審判を終結できる「審判-調停連携制度」の利用を活性化させると発表しました。
「審判-調停連携制度」とは、審判長が審判手続よりも調停[i]による解決が必要と判断した審判事件に対し、両当事者の同意を得て産業財産権紛争調停委員会の調停手続に回付する制度です。審判長と審判官が調停委員として参加し、調停期間は原則6月以内です。
審判-調停連携制度は2021年改正特許法において第164条の2[ii]が新設されたことにより導入されましたが、制度自体があまり知られておらずそれほど活用されていませんでした。そこで特許審判院は、積極的な広報と運営手続きの改善により、審判-調停連携を拡大していくことを計画しています。具体的には、特許審判院は当事者系審判手続で調停制度を積極的に案内し、調停委員として審判官が参加し、審判-調停連携事件の迅速な進行を支援する計画であり、また、韓国大田(テジョン)市にある特許審判院の審判廷を調停会議の場所として提供し、利用者の利便性を高めていく予定です。
特許無効審判等の当事者系審判事件の場合、事件の終結まで長期間を要し、柔軟な紛争解決が難しいことがあり得ます。したがって、当事者系審判事件で審判-調停連携制度を活用すれば、技術的争点に対する専門性と理解度の高い審判官が調停委員として参加することから、迅速かつ柔軟な知的財産権紛争の解決を図ることが期待できます。
(2)「審判–調停連携制度」による半導体関連特許紛争の解決事例
特許審判院は、半導体装備分野の国内企業間での特許無効審判事件が調停による当事者間での迅速な合意を通じて終結したと発表しました。
知的財産権の紛争は審判・訴訟手続きによって解決することが一般的ですが、解決のために長い時間や高額の費用がかかるというデメリットがあります。また、審判・訴訟は勝訴・敗訴といった結果になるため、紛争終結後に当事者間で協力を図ることが難しくなります。
このような点からこれまでは商標・意匠分野を中心に審判-調停連携制度を施行してきましたが、今年特許分野においても同制度を活性化するための制度や手続きを設け、今回韓国の半導体企業間での特許紛争を解決したのが初事例となりました。
特許審判院は、半導体装備にかかる特許について無効理由を判断するに先立ち、紛争の原因を把握した上で対立が高まる前に調停手続きを活用することを勧めました。この意見に両社が同意して当該事件は調停手続きに回付され(2025年3月10日)、審判官が直接参加する調停部が迅速に構成されました。両社は2回にわたる調停会議(2025年4月~5月)と複数回の協議を経て当該特許権を共有することで合意し、3か月で調停成立・事件終結(2025年6月10日)という結果となりました。さらに、両社は納品など協力契約を再開し、今後共同で技術開発を進めることで合意しました。
今回の事例は、単なる紛争解決ではなく両当事者間で協力関係を回復させるという成果を得ることができました。また、世界的に技術開発競争が激しい半導体分野で、国内企業同士で力を合せて韓国の半導体技術の優位を確保し、産業の競争力強化に寄与する事例であると言えます。
(3)日本の調停制度との比較
韓国で特許関連紛争を抱えるリスクを有する日本企業にとって、韓国における「審判-調停連携制度」は、迅速で柔軟な解決の選択肢の一つとなる可能性があり、韓国での今後の運用動向を注視し、制度的に利用することを検討する必要があるかもしれません。その際に、日本において知的財産関連の調停制度活用の実情と、韓国の状況との違いを正しく認識しておくことが好ましいと思われますので、以下、韓国と比較した日本の調停制度について、簡単に触れておきます。
日本では、日本弁護士連合会および日本弁理士会が共同運営する日本知的財産仲裁センター(以下「仲裁センター」)が、知的財産関連紛争の仲裁・調停手続を提供しています。仲裁センターによる調停は、弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力して行なわれ、当事者が合意して和解契約を結ぶことにより事件を解決します。詳細は仲裁センターのサイト(https://www.ip-adr.gr.jp/personal/)をご参照下さい。
仲裁センターの調停は、国際特許紛争等で利用されてはいますが、当事者の費用負担が大きく、利用件数自体は少ないようです。東京地裁・大阪地裁での活用事例はありますが、制度的に連携されているわけではありません。特許庁における審判において、審判官による調停的働きかけがある場合もありますが、韓国のような制度化された審判との連携はありません。
このような状況を鑑みると、韓国の「審判-調停連携制度」は、韓国の特許紛争を「裁判」か「審判」かではなく、柔軟な対話型解決モデルとして制度的に組み込んだ先進的取組であると言えます。
2.特許法施行規則の一部改正
韓国特許庁は、手続的柔軟性を向上させ、行政の効率性を高めるため、2025年4月24日、出願人に対しより親和的且つ予測可能な審査手続きを提供することを目的とした特許法施行規則の一部改正案を立法予告し、当該改正案は、2025年6月4日までの意見聴取を経て、2025年7月11日に公布され、同日に施行されています。
規則改正の主な内容は次のとおりです。
(1)拒絶理由通知に対する意見書提出期間の延長
改正前の特許法施行規則第16条第1項によれば、特許法第63条第1項による拒絶理由通知に対する意見書提出期間として審査官が定めることができる期間は2ヶ月以内と限られていました。
この2ヶ月の意見書提出期間は、他の主要国での意見書提出期間(米国および日本での意見書提出期間は3ヶ月、ヨーロッパおよび中国での意見書提出期間は4ヶ月)に比して相対的に短く、韓国で特許出願をした出願人としては、制限された期間内に拒絶理由を十分に検討および対応することが困難になる可能性があり、意見書提出期間の延長を申請せざるを得ない場合、手続的・財政的な負担を負うことがありました。
この問題を解決するため、改正施行規則では、拒絶理由通知に対して審査官が定めることができる意見書提出期間をヨーロッパおよび中国と同様に4ヶ月以内に延長することとしました。
(2)分割出願への審査猶予制度の適用拡大
今回の特許法施行規則第40条の2第1項第1号[iii]および第40条の3第3項第1号[iv]の改正により、分割出願に対しても、審査猶予申請が可能となりました。具体的には、これらの規則の改正前の条文においては、「ただし書き」において、特許出願が分割出願、分離出願[v]または変更出願である場合は、特許可否決定の保留が許容されていませんでしたが、今回の改正により、この「ただし書き」から「分割出願」が除かれ、特許出願が分割出願である場合にも、特許可否決定を保留することができることになりました。
「審査猶予制度」は、出願人の申請により審査を受ける時点を遅らせる制度であって、出願人は、審査請求日から9ヶ月以内に審査猶予を申請し、猶予可能期間[審査請求日から2年経過の後、出願日から5年(実用新案の場合は出願日から3年)以内の期間]中において任意の時点を指定して審査を開始できるようにする制度です。この改正により、改正規則施行日(2025年7月11日)の時点で既に出願されていて、猶予申請期限(審査請求日から9ヶ月)が過ぎていない分割出願に対しても審査猶予申請が可能です。
今回の改正により、商用化に一定時間がかかる通信・バイオ分野などで、戦略的に審査される時期を調節することが可能となりました。
3.その他の韓国特許庁の取組動向
(1)デザイン審査基準の改正
特許庁はデザイン出願人の便宜と権利保護の強化のため、「デザイン審査基準」を改正し、6月16日から施行しています。
今回改正された審査基準は、企業、デザイナーなどとの現場での疎通過程で提示された内容を反映して審査実務の効率性を強化し、利用者中心のデザイン制度を作ることに焦点を合わせて、以下のような改正を行ないました。
(i)デザインの類似性の判断基準に関する変更
まず、デザインが類似しているかどうかの判断基準について、改正前は2件以上の類似した出願があり両デザインが互いに類似していても、一方は全体デザイン、もう一方は部分デザインで出願されたというだけで審査過程において類似していないと判断され、2件とも登録決定を受けることがありました。改正後には、2件以上の類似した出願がある場合、全体デザインまたは部分デザインで出願されたかどうかに関係なく、デザインの類似性を判断して登録可否を決定することによって、類似デザインの登録を防げるようにしました。
(ii)デザインの説明の記載の簡素化
また、デザインの説明に関する記載について、改正前は出願書にデザインを表現する「図面」と「デザインの説明」を記載する必要がありましたが、改正後は審査官が出願デザインを十分に理解できれば材質や用途などの記載がなくてもこれを拒絶理由とすることができないようにしました。
(iii)自動車の内装のデザインの登録事例の提示
さらに、自動車の内装デザインについて、改正前は明確な審査規定がありませんでしたが、改正後は、メーターパネル、ハンドル、シフトレバー、シートなどで構成された自動車内部のデザインの組合せについて具体的な登録認定事例を提示しました。
(2)改正された特許法、商標法およびデザイン保護法の施行
2025年1月に公布された改正特許法、商標法およびデザイン保護法が、2025年7月22日に施行されました。
(i)改正特許法の主な改正事項
今回の改正による主な改正事項は次の3項目です。
➀発明の実施行為に「輸出」を追加
②医薬品特許権の存続期間の上限および延長可能な特許件数の制限の設定
③秘密取扱命令の違反時の制裁規定の導入
改正特許法の上記各改正事項の内容については、弊所ホームページで2025.4.4付配信の韓国関連記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/13324/)の項目「4.特許法改正(2025年1月公布、7月施行予定)」をご参照下さい。
(ii)商標法およびデザイン保護法の主な改正事項
商標法およびデザイン保護法については、主として下記の点が改正されました。
➀商標権及びデザイン権侵害に対する懲罰的損害賠償の限度引き上げ
改正施行された商標法とデザイン保護法は、侵害行為が故意的な場合、法院が認めた損害額の最大5倍まで賠償を命じることができるように懲罰的損害賠償の上限を従来の3倍から5倍へ引き上げられました。これは、既に「特許法」と「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」で導入されている5倍賠償制度とともに、権利者の実質的な被害救済を強化し、侵害行為に対する予防効果を高めるものと期待されます。
②商標異議申立期間の短縮
従来の商標法では、商標出願公告日から2ヶ月以内に第三者が異議申立をすることができましたが、改正法施行以降はその期間が30日に短縮され、商標出願人はより迅速に登録手続きを終え、権利を早期に確保できるようになりました。
(3)特許権の信頼性と安定性向上のための、予定される特許無効審判制度改正
特許審判院は、特許権の信頼性と安定性を高めるため、特許無効審決予告制の導入と審理手続の厳格化を骨子とした特許無効審判制度の改善に向けた法改正を推し進めています。
(i)特許無効審決予告制について
特許無効審決予告制は、特許無効審判で審判部が請求に理由があると判断した場合、無効審決を下す前にこれを特許権者に前もって予告する制度です。これにより、特許権者は訂正請求を通して自分の権利を有効な状態に維持できる機会を確保できるようになります。
(ii)審理手続の厳格化について
特許無効を主張する請求人は、より具体的かつ明確な証拠を提示しなければならず、証拠提出期限も厳格に守るように求められ、また、口述審理の前に事前の争点整理を行ない、両当事者の主張と立証が十分に行われるように制度が改善されました。
さらに、特許無効審判を請求する際に、請求人は請求項の解釈に対する意見を記載するように勧告されます。また、請求項の解釈に争いがあるか不明確な場合は、当事者に追加の意見提出および立証の機会を付与する方式を採用し、審判の正確性および公正性の向上を図っています。
上記(i)および(ii)のような制度の改善は、特許が無効かどうかに対する判断のための基準と手続きを明確にし、特許権者による訂正の機会を拡大することで、特許権の質的向上と実効性のある権利保護に寄与するものと思われます。
このような制度改善のための法改正は今年(2025年)下半期に発議される予定です。
[情報元]
1.[Lee International IP & Law] Newsletter Summer 2025「特許審判院、審判-調停連携制度活性化本格推進」2025年7月17日
https://www.leeinternational.com/home/bbs/board.php?bo_table=Newsletter2025_SUM&wr_id=11
2.Kim & Chang [IP Legal Update](2025年7月9日)「特許法・実用新案法施行規則改正:意見書提出期間を4ヵ月とし、分割出願の審査猶予も可能に」
https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=32615&lawCurPage=2&lawSchSection=4&kncCurPage=1&kncSchSection=3&scroll=1100
3.Lee International「拒絶理由通知書への対応期間の拡大(4ヶ月)及び分割出願への審査猶予制度の適用拡大(2025年7月11日施行)」25-07-10
https://www.leeinternational.com/home/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=103
4.[Lee International IP & Law] Newsletter Summer 2025 「主要知的財産権の保護と活用強化」25-07-17
https://www.leeinternational.com/home/bbs/board.php?bo_table=Newsletter2025_SUM&wr_id=8
5.ジェトロソウル事務所 知的財産ニュースより
(1)韓国特許庁特許審判院、今年から「審判-調停連携制度」の利用活性化を促進(2025年3月24日)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2025/250324a.html
(2)特許審判院、「審判-調停連携制度」により半導体特許紛争を解決(2025年6月26日)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2025/250626b.html
(3)意見書提出期間の延長や分割出願の審査猶予の内容を盛り込んだ特許法・実用新案法施行規則を一部改正(2025年7月8日)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2025/250708.html
6.HA&HA特許・技術レポート2025-7「出願人の便宜・権利保護の強化」特許庁、デザイン審査基準を改正」
http://haandha.com/html/jp/media_letter-view.php?no=115&search=&search_text=&start=0
7.[Lee International IP & Law] Newsletter Summer 2025「特許審判院、特許権の信頼性と安定性向上のための無効審判制度改善推進」25-07-17
https://www.leeinternational.com/home/bbs/board.php?bo_table=Newsletter2025_SUM&wr_id=10
担当 深見特許事務所 野田 久登
[i] 調停は、裁判外紛争解決手続き(ADR、Alternative Dispute Resolution)の一つであって、当事者との間に利害関係を有しない公平・中立な第三者である調停人が、紛争を抱えた当事者の間に入り、和解の成立に向けて協力する制度です。
[ii] 第164条の2(調停委員会の回付)
➀審判長は審判事件を合理的に解決するために必要と認めれば、当事者の同意を受け、該当の審判事件の手続を中止し、決定として該当事件を調停委員会に付することができる。
②審判長は第1項により、調停委員会に付したときには該当審判事件の記録を調停委員会に送付しなければならない。
③審判長は調停委員会の調停手続きが調停不成立で終了されれば、第1項による中止決定を取消し審判を再開し、調停が成立された場合には該当審判請求は取下げられたものとみなす。
[iii] 特許法施行規則第40条の2(特許可否決定の保留)
①審査官は、特許出願審査の請求後出願人が特許出願日から6ヶ月以内に別紙第22号の2書式の決定保留申請書を特許庁長に提出する場合には、特許出願日から12ヶ月が経過する前まで特許可否決定を保留することができる。但し、次の各号に該当する場合には、この限りでない。
1. 特許出願が分離出願または変更出願である場合(以下省略)
[iv] 特許法施行規則第40条の3(特許出願審査の猶予)
①特許出願人が出願審査の請求をした場合であって、出願審査の請求日から24ヶ月が過ぎた後に特許出願に対する審査を受けようとするなら、出願審査の請求日から9ヶ月以内に……審査猶予申請書を特許庁長に提出することができる。但し、(中略)
③審査官は、第 1 項による審査猶予申請がある場合には、猶予希望時点まで特許出願に対する審査を猶予することができる。但し、次の各号にあたる場合にはこの限りでない。
- 特許出願が分離出願、変更出願または正当な権利者の出願である場合
[v] 「分離出願」については、弊所ホームページにおいて2022.12.26付で配信された「韓国と日本の類似する特許制度における留意すべき相違点」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/9056/)の項目「2.(2)分離出願制度の導入(特許法第52条の2新設)」をご参照下さい。