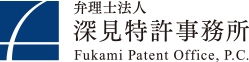市販製品が技術水準に属するかどうかに関する付託G1/23への拡大審判部の回答
欧州特許条約(EPC)に基づく新規性および進歩性(inventive step)を評価する際の先行技術(prior art)を構成するために、特許出願が提出される前に市販されている製品が当業者によって分析および複製(あるいは再現)可能でなければならない範囲を明確にすることを目的として、2023年6月に、欧州特許庁の最高の法的機関である拡大審判部に付託が行われました。
この付託に対して拡大審判部は、2025年7月2日付で決定を発行し、その中で、「欧州特許出願日より前に市場に出された製品は、その組成または内部構造をその日より前に当業者が分析および複製することができなかったという理由のみで先行技術から除外されるべきではない」と結論付けました。
1.事案の背景
本件は、欧州特許EP2626911(以下「本件欧州特許」)に対する異議申し立てを却下する、異議申立部門の決定に対して提起された審判T438/19[1]に関連しています。この審判では、本件欧州特許のクレーム1の主題が進歩性を有するかどうかを判断するために、市販製品(商標ENGAGE®8400で販売されている複合ポリマー)が特許の有効出願日より前に一般に公開されていたかどうか、したがって最も近い先行技術となり得るかどうかを立証する必要がありました。
付託を行なった審判部は、この分野の以前の判例法では解釈が相違しており、市販の製品がいつ技術水準(the state of the art)と見なされるかについて法的な不確実性が生じていると指摘しました。特に、付託した審判部は、技術水準と見なされるために、市販製品が分析可能で再現可能でなければならない程度に関して、さまざまな解釈があることを強調しました。
G1/23で拡大審判部に付託された質問は、以前の拡大審判部の決定G1/92[2]によって導入された再現性基準の可能性に関する解釈の相違に起因しています。特に、この以前の決定では、製品の化学組成は、製品が当業者によって分析および再現できる場合にのみ、技術水準(the state of the art)を表すことが要求されました。
この事件の背景に関する詳細は、弊所HPにおいて2023年9月25日に配信した、本件付託に関する記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/10088/)をご参照下さい。
2.付託における3つの質問事項と、それぞれに対する拡大審判部の回答
(1)付託された質問事項
審判T438/19において、以下の質問が拡大審判部に付託されました。
[質問1]欧州特許出願の提出日より前に市場に投入された製品は、その組成または内部構造をその日より前に当業者が過度の負担なしに分析および複製できなかったという唯一の理由で、EPC第54条(2)の意味の範囲内での技術水準から除外されるか。
[質問2]質問1の答えが「いいえ」の場合、出願日より前に一般に公開された当該製品に関する技術情報(例えば、技術パンフレット、非特許文献または特許文献)は、その日以前に当業者が過度の負担なしに製品の組成または内部構造を分析および複製できるかどうかに関係なく、EPC第54条(2)の意味の範囲内での技術水準であるか。
[質問3]質問1の答えが「はい」の場合、または質問2の答えが「いいえ」の場合、決定G1/92の意味の範囲内で、製品の組成または内部構造を過度の負担なしに分析および再現できるかどうかを判断するために、どの基準が適用されるか。特に、製品の組成と内部構造が完全に分析可能で、まったく同じ再現性を備えている必要があるか。
(2)付託に対する拡大審判部の回答
上記各質問事項に対して、拡大審判部の決定では、次のように回答しました。
(i)質問1について
G1/92には、製品が再現可能でなければならないという要件(再現性の要件)が明示されており、製品を再現するには、市場から容易に入手可能な形態で製品を入手する方法と、当業者自身の技術的能力に応じて自らが製品を製造する方法の2通りがある。G1/92の再現性の要件は、後者のみならず前者も含むと解釈されるべきである。
したがって、(前者の意味での再現性を満たせば技術水準となるので)後者の意味での再現性を満たさないからという理由のみで技術水準から除外されるのか、という質問1への回答は「いいえ」となる。
(ii)質問2について
上記後者の意味で「再現」できない製品であったとしても、上記前者の意味で「再現」できることで技術水準に含まれるのであれば、その製品の関連技術情報も当然技術水準に属するはずである。したがって、質問2への回答は「はい」である。
(iii)質問3について
質問1および2への上記回答から、質問3は議論の余地がない。
(3)結論
拡大審判部の回答は、製品の非再現性は、その製品および関連する技術情報が技術水準の一部を形成することを妨げることはできないと結論付けています。拡大審判部の結論は、欧州の実務を、米国の特許実務に見られる「on-sale Bar」基準と一致させる役割を果たしていることが注目されます。ここで、米国における「on-sale bar」とは、「特許出願の1年前の基準日(the critical date)よりも前に、販売されている(on sale)発明については、誰も特許を取得する資格はないという原則(新規性阻害事由)」を言います。「on-sale bar」についての詳細は、弊所HPの国・地域別IP情報において2022年8月15日付で配信した米国関連記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8386/)をご参照下さい。
3.以前の拡大審判部の決定G1/92の適切な解釈について
(1)「複製(あるいは再現)可能」の解釈について
G1/23で拡大審判部に付託された質問に関連する以前の拡大審判部の決定G1/92では、製品の化学組成は、製品が当業者によって分析および複製(すなわち再現)可能である(can be reproduced)場合にのみ、技術水準を表すことが要求されました。G1/23における拡大審判部の決定は、この文言がどのように解釈されるべきかに重点を置いた内容になっています。
拡大審判部は、G1/92の「複製(あるいは再現)可能」という文言は、判例法では、製品が特定の出発原料から「製造可能(manufacturable)」であることを要求するものとして通常解釈されていると特定しました。実際、拡大審判部は、G1/92でなされた決定とG1/23で言及された質問は、この解釈が採用された場合にのみ「意味がある」と強調しました。
この解釈を進めて、拡大審判部は、G1/92の2つの可能な解釈が利用可能であると考えました。
[解釈1]組成物(したがって製品)を再現できない場合、製品自体は技術水準の一部ではないか、又は
[解釈2]組成物(したがって製品)を再現できない場合、製品の組成だけが技術水準に属さず、製品自体とその再現可能な特性は技術水準に属する。
(2)拡大審判部の判断
しかし、拡大審判部は、どの解釈が採用されるかに関係なく、「明らかに不条理な」結果が導かれると指摘しました。具体的には、拡大審判部は、すべての人工材料は、最終的には、たとえば化学元素のような、一般的知識を使用して当業者が作ることができない出発物質に戻ることになり、そのような出発物質は再現性がないことから、上記の解釈のいずれに従ったとしても、すべての出発物質が技術水準とは見なされないことになると結論付けました。再現不可能な出発物質が技術水準の一部を形成していないことが判明した場合、その出発物質に由来する製品も技術水準から排除する必要があることから、拡大審判部は、これは「自然界の如何なる材料も技術水準に属さない」という状況につながると強調しました。
常識的に考えると、当業者にとって製造可能かどうかの判断に際して、その出発物質の特定のために化学元素のようなものにまで遡る必要はなく、当業者が通常入手し得る材料を出発物質と考えるのが妥当ではないかとの疑問が生じ得ます。拡大審判部は、「製造できなければ再現不可能であるとすれば先行技術(あるいは技術水準)に含まれない」とする解釈を過度に厳密に適用すると、如何なる人工物も最終的には当業者が製造できない原材料(元素など)に帰することになり、すべての人工物が「複製(あるいは再現)不可能」として先行技術から除外されるという、明らかに不合理な帰結となると指摘しました。この論法は、G1/92の「再現可能性」の要件を文字通り解釈すべきではないとの立場を補強するために、拡大審判部が用いたものであると解されます。
(3)結論
上記を考慮して、拡大審判部は、G1/92で採用された「複製可能」という文言をより広く解釈し、市販されている形で容易に入手可能な状態で市場から製品を入手することを包含すべきであると指摘しました。拡大審判部は、この解釈は、当業者として自然で合理的な行動である市場からの入手を再現可能性の一方法として合法的に認めるものであり、再現性の要件は、市場に存在する製品によって本質的に満たされることになることを強調しました。
このような解釈の結果、拡大審判部は、G1/92の適切な解釈は、「製品の化学組成は、製品自体が一般に公開され、当業者が分析できる場合、製品の組成をあえて深く分析しようという特別な理由の有無とは無関係に、すなわち主観的動機や背景事情に関わらず、客観的に当業者が分析できる場合、技術水準となる」との見解を示しました。
この解釈に基づいて拡大審判部は、「市場に出回る製品のすべての分析可能な特性は、技術水準に属する、つまり、当業者が認識し、技術的解決策を検討する際に依拠する技術情報を表す」と指摘しました。
4.本件判決の影響
(1)特許製品の販売時期を考慮した特許出願戦略の重要性
G1/23における拡大審判部の決定の影響は広範囲に及ぶものと考えられます。最も単純な意味では、この決定は、特許製品が市場に出された場合、当業者がその製品の有形の複製物を入手できるため、当業者が「複製可能」であるかどうかにかかわらず、市場に出された製品は先行技術となるという点で、常識的なアプローチと見なすものを採用していると言えます。言い換えれば、「市販されたものは、特別な分析や技術的推測なしに、当業者が手に取れるものとして、それ自体が先行技術と見なされる」と判断しています。したがって、拡大審判部の決定は、先行技術の範囲を広げ、特許出願戦略として、製品の発売時期との関連でのタイミングの重要性をさらに強調していると言えます。
(2)分析の動機について
拡大審判部の決定は、市販された製品が、その製品の分析可能な機能とともに技術水準の一部になり、当業者がその製品を分析しようとする特別な動機がある必要はないと指摘しています。すなわち、当業者によって製品の分析が可能であれば、それ自体が先行技術と見なされ、分析しようとする理由の有無は副次的な問題に過ぎないと考えられています。
(3)分析の範囲の法的許容範囲について
拡大審判部は、分析可能な特性は先行技術として扱われると明言する一方で、製品の分析に際してどのような手法が許容されるのかについては、明確な線引きを示しませんでした。そのため、「法的な分析の限界(legal limits)」が今後の重要な議論の対象となる可能性が高いものと予想されます。
ここで、「法的な分析の限界」とは、たとえば次のものが考えられます。
(i)物理的・科学的分析手法の許容範囲
市販製品に対して、どのような分析手法(たとえば、破壊的分析、逆解析[3]、ナノスケール分析[4]等)が許容されるのか。特に再現性を欠く製品や気密性の高い製品(医薬品、特殊素材等)において、どこまでが正当な分析と言えるのか。
(ii)取得された情報の先行技術としての法的有効性
製品のある特性が技術的に分析可能だとしても、その分析結果が公知であることの証拠として法的に適格かどうか。
(4)新規性と進歩性との先行技術の判断の相違
拡大審判部の決定は、市場に出回る製品の先行技術としての位置付けについて、新規性と進歩性との状況を区別していることに注意することも重要です。特に、拡大審判部は、新規性のために「発明と技術水準との比較は、当業者からの特別な動機を必要としない」ことを強調しています。これは、新規性判断においては当業者が先行技術を比較しようという動機があったかどうかは重要ではないという意味であり、言い換えれば、市場に出された製品については、それが当業者にとって気に留める動機がなかったとしても、それが新たな発明と比較された時点で先行技術として扱われるという立場を意味します。
一方、進歩性の評価においては、当業者が、市販製品について、例えばそれに付随する情報が不十分であるために、当該製品を先行技術としては無視する正当な理由がある場合には、そのような事情を考慮して先行技術から除外する可能性があります。進歩性を審査する際に、再現不可能であるが公開されている(publicly available)製品またはその特性をどのように考慮できるかについて、正式かつ厳格な決まりはありません。その結果、進歩性の評価に関しては、拡大審判部の決定は、市場に出回っている製品が最も近い先行技術であると見なすことができるかどうか、およびその製品に変更を加えることが自明であるかどうかは、特定の事件の事実に大きく依存することを示唆しているように思われます。
[情報元]
1.D Young & Co Patent Newsletter No.108 August 2025 “G1/23 and enablement: are commercially available products state of the art?”(August 1, 2025)
https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/G1/23-enablement-state-art
2.Press Communiqué of 2 July 2025 concerning decision G1/23 (“Solar cell”) of the Enlarged Board of Appeal(本件に関するプレスコミュニケ原文)
3.July 2, 2025付拡大審判部の決定(G1/23)原文全文
4.D Young & Co “G1/23: assessing whether commercially available products are prior art”(August 1, 2023)
https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/G1/23-prior-art
5.ジェトロ デュッセルドルフ事務所「欧州特許庁(EPO)審判部、先行技術を構成する技術水準の解釈についての拡大審判部審決を公表」2025年7月28日
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2025/20250728.pdf
[担当]深見特許事務所 野田 久登
[1] 審判T438/19の中間決定原文のURL
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t190438ex1
[2] 拡大審判部の決定G1/92原文のURL
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g920001ep1
[3] 「逆解析」とは、観測された結果(データ)から、その結果を導いた原因となる入力値(条件、設計変数)を求める分析手法を言います。
[4] ナノスケール分析とは、原子から百ナノメートル程度の微細スケールで物質の構造や組成を解析する手法を言います。