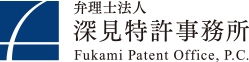UPC控訴裁判所における「主題の追加」に関する最近の重要判決紹介
欧州特許庁(EPO)は、「主題の追加(added subject matter)」に関しては非常に厳格な審査基準を適用することで知られています。一方、主題の追加に関して統一特許裁判所(UPC)がEPOと同様の厳格な基準を適用するのかあるいは独自の基準を採用するのかについては、実務上の重要事項として注目されています。近時UPCでも主題の追加に関する判決が下されており、これらの判決を検証すると、UPCがEPOに比べてやや緩やかなアプローチを取ろうとする傾向が見られます。
本稿においては、まずEPOの主題の追加に関する審査基準について説明し、これに対してUPC控訴裁判所が主題の追加に関して最近下した重要な判決であるAbbott v Sibio事件判決を紹介します。
1.主題の追加に関するEPOのアプローチ
(1)「ゴールドスタンダード」テストについて
欧州特許条約(EPC)では、主題の追加は、以下に示す第123条(2)において規定されております。
**********
Article 123 Amendments
(1)(省略)
(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
(欧州特許出願または欧州特許は、出願当初の内容を超えて拡張する主題を含むように補正することはできない。)
(3)(省略)
**********
EPOは、EPC第123条(2)の規定を取り扱う際に、「補正によって、当業者にとって暗黙の事項を考慮した上で、出願当初の出願内容から直接かつ明確に導き出せる情報が当業者に提示されているかどうか」を問うテストを適用し、直接かつ明確に導き出せない情報が提示されているような場合には、当該補正は、出願当初の出願内容を超える主題を導入するものとみなされることになります。2011年8月30日付けの拡大審判部の審決(G 2/10[i])において、このようなテストは、絶対的基準を意味する「ゴールドスタンダード(gold standard)」テストと呼ばれるようになりました。
実際には、このゴールドスタンダードテストではしばしば、当初の出願で使用された文言をほぼ文字通りに評価することがあります。このような厳格なアプローチは、カンマの欠落といった些細な理由で欧州特許が取り消されるような事例(T 1127/16[ii] および T 1473/19[iii])を生じさせました。特に、審決T 1473/19については、弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2023年9月25日付け配信記事「クレーム中のカンマの欠落によりクレームと明細書とに不整合が生じ特許が取り消されたEPO審決」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/10089/)において詳細に解説しておりますのでご参照ください。
(2)中間的一般化に対するEPOのアプローチ
クレームが、特定の実施形態から分離された特徴を含めるように補正された場合、または特定の実施形態から特徴を省略するように補正された場合、状況は複雑になります。そのような場合、補正後のクレーム中に残った1つまたは複数の特徴は、クレームからは省略された1つまたは複数の他の特徴と組み合わせた形でのみ出願時の出願書類に記載されていることになります。
上記のように補正がいわゆる中間的一般化を生じさせるような状況において、そのような中間的一般化がEPC第123条(2)の下に許容されるものか否かを判断するために、EPOは、実施形態から分離された(または省略された)特徴と他の特徴との間に構造的および機能的な関係があるかどうかを調べます。EPOはまず、当該特徴が実施形態の他の特徴と密接に関連しているかどうかを判断します。次に、出願全体の開示内容が、当該特徴の分離とクレームへの導入(またはクレームからの省略)を正当化するかどうかを判断します(中間的一般化についてはEPOの審査基準H-V 3.2.1 “Intermediate generalisations”を参照[iv])。この基準を満たさない補正は、EPC第123条(2)に違反する、許容されない中間的一般化であると判断されます。
2.UPC控訴裁判所における主題の追加に関する重要な判決
(1)事件の経緯
Abbott Diabetes Care Inc.(以下、「Abbott社」)は、欧州特許第3831283号(以下、「本件特許」)を所有しています。本件特許は、原出願(後に欧州特許第3300658号として発行したEP出願)からの分割出願に基づいて成立した特許であり、この原出願は、PCT出願(WO 2013/090215として公開)からEP広域段階に移行されたEP出願であります。
Abbott社は、Sibio Technology Limited他1社(以下、「Sibio社」と総称)に対する仮差止命令の請求をUPCのハーグ地方部に申し立てました(Abbott v Sibio事件:UPC_CFI_131/2024)。
(2)ハーグ地方部の判断
本件仮差止命令請求事件における種々の争点の中で、被告であるSibio社は、当初出願(元のPCT出願)においては組み合わされて開示されている複数の特徴のうちの特定の特徴がクレーム1においては省略されていることが許容されない中間的一般化に該当するため、クレーム1は追加された主題を含んでおり本件特許は無効である、と主張しました。より具体的には、本件特許のクレーム1にクレームされた血糖値測定装置において、そのベース部分の凹部からエラストマーシールが省略されていることが、許容されない中間的一般化に該当するかどうかが争点になりました。原告であるAbbott社は、本件特許の図面の一部にエラストマーシールが欠落していることから証明されるように、エラストマーシールは必須の特徴ではないと主張しました。これに対して、被告であるSibio社は、エラストマーシールは凹部との組み合わせで一貫して開示されていると主張しました。
Sibio社が主張したように、本件特許の特定の実施形態はセンサと電子回路との間の結合を密閉するためにエラストマー材料または弾性材料を使用しております。たとえば図47A-47Cの実施形態に関しては、電子回路アセンブリの筐体に直接形成された凹部はエラストマーシール部材を含むことが述べられています。
ハーグ地方部は、EPOの「ゴールドスタンダード」テストを明示的に適用しました。そして、エラストマーシールと凹部との間には構造的・機能的関係が存在すると判断し、クレーム1にエラストマーシールが欠落していることは、許容されない中間的一般化であるとの結論を下しました。この結果、ハーグ地方部は、Abbott社の仮差止命令の請求を却下しました。Abbott社は、ハーグ地方部の判断を不服としてUPCの控訴裁判所(ルクセンブルク)に控訴しました(UPC_CoA_382/2024)。
(3)控訴裁判所の判断
UPC控訴裁判所はハーグ地方部の判決を覆し、Abbottに仮差止命令を認めました。これは、控訴裁判所が、主題の追加の評価において、EPOで採用されてきた、当初の出願で使用された文言をほぼ文字通りに評価するような厳格なゴールドスタンダードテストのアプローチに比較して、より全体論的なアプローチを採用したことによります。
控訴裁判所は、EPOの厳格なアプローチに対比してUPCの全体論的アプローチを特徴付ける重要な基準を、「当業者が、出願当初の出願内容全体から、出願日を基準として一般的な知識を用いてかつ客観的に見て、何を直接かつ明確に導き出すであろうかということであり、これにより、暗黙的に開示された主題、すなわち明示的に記載された事項から明確かつ明瞭な帰結となる事項も、出願内容の一部として考慮されるべきである」と特徴付けました。控訴裁判所が示した一般原則はEPOの「ゴールドスタンダード」アプローチと一致しているものの、UPC控訴裁判所は暗黙的に開示された主題の考慮をより重視しました。
この基準を適用したUPC控訴裁判所は、クレーム1には許容されない中間的一般化は含まれていないと判断しました。重要なのは、控訴裁判所が、出願内容に基づいては、2つの特徴が分離可能であるとは判断しなかったことです。すなわち、控訴裁判所は、明細書の記載から、湿度や汚染物質によってセンサの接点と電子回路の接点とがショートし、装置の機能に障害が生じることを防止するために密閉が重要であることを認めました。しかしながら、当初の出願は、密閉を実施するための様々な方法を開示しており、それらの方法は、エラストマー材料を使う方法以外の方法を含んでおります。
このように、当初の出願に開示された理由により、接点に対する密閉の必要性は当業者にとって明白ですが、控訴裁判所は、特定の種類のシールの利点と欠点に関する指針が明細書に示されていないことに注目しました。したがって、控訴裁判所は、エラストマーシールによる密閉の機能について検討した場合、当業者は「エラストマーシールの使用が本発明の全体的な目的および効果を達成するために必要であるとは考えないであろう」と確信しました。これによって、控訴裁判所は、Abbott社による、エラストマーシールは必須の特徴ではないとの主張を認め、クレーム1の主題は、密閉材料としてエラストマーシール材料の使用を省略したことによって当初出願の内容を超えて拡張するものではなく、主題の追加に該当しないとしてSibio社の主張を退けました。
3.主題の追加に関するその後のUPCでの判決
Abbott v Sibio事件の控訴審判決は、Hurom Co., Ltd(以下、「Hurom社」)の所有するジューサに関する欧州特許第3155936号に関して、Hurom社がNUC Electronics Co., Ltd他数社(以下、「NUC社」と総称)を特許侵害でUPCパリ地方部に訴えたHurom v NUC事件(UPC_CFI_163/2024)において、パリ地方部によって直接適用されました。
NUC社が提示した主要な主張は、出願当初の従属クレーム3では、クレームされたジュース搾りモジュールの駆動軸と電源コネクタとの間に第1シャフトギアが「介在」していることが要求されていたというものでした。審査中に、従属クレーム3は、駆動軸、電源コネクタ、および第1シャフトギアが単に「互いに接続されている」ように補正されていました。この文言は、UPCでの審理中に主請求のクレーム1に挿入されました。
当初の出願には「接続されている」という文言の逐語的な根拠はなく、NUC社は、この文言は当初出願の内容を超えて拡張されていると主張しました。しかし、パリ地方部は、明細書に2つの実施形態が記載されていることに着目しました。1つは元の「介在」という表現を用い、もう1つは第1シャフトギアが電源コネクタに「係合」していることを要件としていました。
パリ地方部は、補正後のクレーム1の「接続されている」という表現は「両方の実施形態を網羅する適切な概念」であると判断しました。パリ地方部は、ブラシ回転手段(第1シャフトギアを含む)の構造は「自由に変更可能」であるとする明細書中の更なる段落を引用しました。これにより、パリ地方部は、当業者は第1シャフトギアの構成を過度に文字通りに解釈すべきではなく、クレームには追加の主題は含まれていないと判断しました。
4.結論
過去2年間に渡って、UPCにおけるいくつかの第一審判決は、主題の追加に関するEPOの「ゴールドスタンダード」テストを適用してきました(例えば、ORD_598459/2023、ORD_598482/2023、ORD_598564/2023、およびUPC_CFI_131/2024)。このことから、このテストがUPCにおいて標準となることが予想されました。実際、UPC控訴裁判所が主題の追加に関するその最初の審理において示したアプローチは、EPOのアプローチと概ね一致しているように見えます。しかしながら、UPC控訴裁判所は現在、当業者であれば、特に発明の全体的な目的と効果に鑑み、当初の開示全体から何を暗黙的に理解するかをより積極的に検討しているように思われます。
UPCのパリ地方部のNUC v Hurom事件における判決は、EPOが主題の追加に関する異議を審査したであろう方法とは対照的です。EPOの異議部および審判部は、「ゴールドスタンダード」を適用する際に、当初のクレームまたは明細書の逐語的な文言に基づかない補正に対して厳しい姿勢を取ることがよくあります。しかしながら、EPO審判部は、UPCとEPOとが主題の追加に関して一致していることを示すことに熱心であるように見えます。EPOの最近の審決であるT 1535/23[v]において、EPO審判部は、係争対象の特許のクレーム1から特徴を省略することは、許容されない中間的一般化に相当すると結論付けました。興味深いことに、EPO審判部はその決定において、Abbot v Sibio事件におけるUPC控訴裁判所のアプローチに直接言及し、これらのアプローチはそれぞれの事件の事実に大きく依存しており、したがって矛盾するものではないと指摘しました。
UPCの新たなアプローチが、主題の追加に関する他の係争においてどのように解釈されるかはまだ不明です。例えば、次のような疑問点が存在します:
・UPCにおいて、特許権者が構成要素の別々のリストから選択すること、たとえば明細書に掲載された別々のリストに挙げられた数値等を任意に組み合わせてクレームに記載するようなこと、を正当化することが容易になるのか?
・UPC控訴裁判所がクレーム補正をより広範な明細書の文脈で扱うことを望んでいることを考えると、欧州特許出願明細書において一般に実施形態の説明の末尾等に記載される、ある実施形態の特徴が別の実施形態の特徴と組み合わせられる可能性があることを示唆する包括的な「定型文」の文言の重要性は高まるのか?
UPCの控訴裁判所が出願時の出願内容全体を考慮に入れることを強調したことは、控訴裁判所がクレーム解釈に際して明細書および図面は常に使用しなければならないと判示したNanoString v 10x Genomics事件判決で確立されたクレーム解釈の原則[vi]と一致しています。このNanoString v 10x Genomics事件判例は、急速に発展を続けるUPC判例法において依然として大きな影響力を持ち続けており、ほぼすべての実体判決で引用されているだけではなく、UPCにおいてEPCを解釈するための標準的実務を定める上で控訴裁判所が影響力を及ぼしてきたことを改めて示すものでもあります。主題の追加に関する本件訴訟(Abbott v Sibio事件)の控訴裁判所の判決がNanoString v 10x Genomics事件判例と同様の効果をもたらし、EPOの「ゴールドスタンダード」テストよりも寛容なアプローチがUPCの標準となるかどうかは、現時点ではまだ何とも言えません。
[i] https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/g100002ex1.pdf
[ii] https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t161127eu1.pdf
[iii] https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t191473eu1.pdf
[iv] https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2025/h_v_3_2_1.html
[v] https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t231535eu1.pdf
[vi] 弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2025年9月18日付け配信記事「UPCにおけるクレーム解釈の原則に関する最近の判決紹介」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/14336/)において詳細に解説しておりますのでご参照ください。
[情報元]
1.D Young & Co, IP Cases & Articles “Unified Patent Court: added subject matter”(August 1, 2025)
https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-added-subject-matter
2.Abbott v Sibio事件の控訴審判決原文
3.NUC v Hurom事件の第一審判決原文
[担当]深見特許事務所 堀井 豊