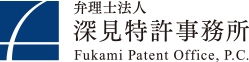自明性の推定は、当業者の動機と期待に関する事実認定に基づいていなければならないと認定し、地裁の特許有効性の判断を支持したCAFC判決
米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、長時間作用型注射用投薬計画(a long-acting injectable dosing regimen)に関連する特許クレームの有効性を支持するニュージャージー連邦地方裁判所(以下「地裁」)の判決を(2回目の控訴審で)支持し、自明性の推定は自動的に適用されるわけではなく、特に当業者の動機と期待に関する事実認定に基づいていなければならないと認定しました。
Janssen Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Case No. 25-1228 (Fed. Cir. July 8, 2025) (Prost, Reyna, Taranto, JJ.)
1.事件の背景
(1)本件特許の概要
Janssen Pharmaceuticals, Inc.(以下「Janssen社」)は、統合失調症治療薬であるパルミチン酸パリペリドン(paliperidone palmitate)の投薬計画(dosing regimen)に関する米国特許(US9,439,906、以下「’906特許」)を保有しています。’906特許は、従来の経口投与と比較して患者のコンプライアンス[i]を改善することを目的とした、約1週間の間隔をあけて2回の「薬剤投与(loading doses)」とそれに続く毎月の維持注射(maintenance injection)[ii]を含む投薬計画(dosing regimen)[iii]を対象としています。’906特許に対応する日本特許として、特許第5825786号があり、技術用語について本稿で用いる日本語訳は、概ね当該日本特許の記載に準拠しています。
’906特許の代表的なクレーム(クレーム1)原文は以下の通りです。
1. A dosing regimen for administering paliperidone palmitate to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder comprising
(i) administering intramuscularly in the deltoid of a patient in need of treatment a first loading dose of about 150 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate formulated in a sustained release formulation on the first day of treatment;
(ii) administering intramuscularly in the deltoid muscle of the patient in need of treatment a second loading dose of about 100 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate formulated in a sustained release formulation on the 6thto about 10th day of treatment; and
(iii) administering intramuscularly in the deltoid or gluteal muscle of the patient in need of treatment a first maintenance dose of about 25 mg-eq. to about 150 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate in a sustained release formulation a month (±7 days) after the second loading dose.
上記クレーム1の試訳を以下に示します。
『1.統合失調症、統合失調症性感情障害、または統合失調症様障害の治療を必要とする精神科患者にパルミチン酸塩パリペリドンを投与するための投薬計画であって、以下の工程を備える。
(i)治療の初日に、持続放出性製剤に製剤化されたパルミチン酸パリペリドンとして約150mg当量[iv]のパリペリドンの初回投入用量(first loading dose)を患者の三角筋に筋肉内投与する工程;
(ii)治療の6日目から約10日目に、患者の三角筋に、製剤化されたパルミチン酸塩パリペリドンとしてパリペリドン約100mg当量の2回目の投入用量を筋肉内投与する工程;および
(iii)第2回目の投入用量を投与した1ヶ月後(±7日後)に、患者の三角筋または殿筋に、持続放出性のパルミチン酸パリペリドンとして約25mg当量~約150mg当量の第1回目の維持用量(a first maintenance dose)を筋肉内投与する工程。』
(2)特許侵害訴訟の提起および当事者の主張
Janssen社は、Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(以下「Teva社」)がJanssen社の医薬品のジェネリック医薬品の承認を求める短縮新薬申請(ANDA)を2017年12月に提出した後、2018年にHatch-Waxman法[v]および米国特許法第274条(e)(2)基づいてTeva社を訴えました。Teva社は、’906特許が有効であると仮定した場合には侵害していることを認めましたが、’906特許の有効性に異議を唱え、すべてのクレームは以下の3つの先行技術文献に照らして自明であると主張しました。
(i)NCT00218548(以下「’548プロトコル」):パルミチン酸パリペリドンを3回(毎回同じ量で)投与する投薬計画が、有効成分を含まない偽薬(placebo)によるプラシーボ効果(placebo effect)[vi]よりも効果的であるという仮説を検証するための臨床試験を詳述していますが、臨床結果や安全性データは含まれていません。
(ii)Janssen社所有の米国特許第6,555,544(以下「’544特許」):筋肉内注射または皮下注射による投与のためのデポ製剤(depot formulation)[vii]として適した医薬組成物であるパルミチン酸パリペリドンの効果を発揮するために必要な量を開示しています。
(iii)Janssen社により出願された国際特許出願の国際公開公報(WO2006/114384、以下「WO’384公報」):無菌結晶性のパルミチン酸パリペリドンを調製するプロセスについて開示しており、特に、25~150mg当量の充填量を記載しています。
またTeva社は、自明性の主張以外に、全クレームについての記載要件不備、粒子径の記載を含むクレームについての不明確性についても主張しました。
(3)地裁の判断
(i)最初の審理における判断
2021年、地裁は、ベンチトライアル(陪審裁判に対する用語であって、裁判官のみが事実認定を行ない、判決を下す裁判)の後、具体的な投入用量、投入順序、三角筋注射の必要性など、クレームと先行技術との間の重要な違いを理由に、Teva社の自明性の主張を却下しました。より具体的には、地裁は、Teva社の主張には、先行技術文献の開示を組合せてクレームの投薬計画に到達する動機や合理的成功の期待の立証が不足していると評価し、Teva社のいう「重なり合う範囲」による自明性の推定は適用されず、本件特許は数値の単なる寄せ集めではなく、固有の組合せであると指摘しました。
また、Teva社の記載要件不備および不明確性の主張について地裁は、成立しないと判断しました。
(ii)初回控訴の提起およびCAFCの判断
上記地裁の判断に対してTeva社は2024年に控訴し、それに対してCAFCは、記載要件不備および不明確性の非成立については地裁判断を支持しましたが、自明性の非成立については、地裁の分析上の誤りを指摘して取消し、さらなる分析のために差戻しました。
(iii)CAFCからの差し戻し後の審理における地裁の判断
差戻し審において地裁は、既存の審理記録と2024年のCAFCの判断を踏まえた当事者の新たな主張に基づき、特許発明の自明性について再検討し、結論として、いずれのクレームについてもTeva社は自明性を立証できなかったと再び判断し、それに対してTeva社は再び控訴しました。
2.2度目の控訴審におけるTeva社の主張およびCAFCの判断
(1)一応の自明性の推定(a prima facie case of obviousness)について
通常、審査官や裁判所が初歩の段階で、「先行技術に基づけば、当業者が容易に発明に到達できたと考えられる」と認めれば、「一見して自明であると推定できるだけの一応の立証」がなされたものと判断されます。たとえば、クレームされた組成物の特性等の数値範囲が先行技術に開示された数値範囲と重なる場合には、一見して自明であるとの一応の立証ができれば、一応自明であると推定されます。
Teva社は、先行技術がクレームに記載の範囲内の投入用量(150または100 mg当量)を開示しているため、自明性の推定が適用されるべきであると主張しました。
CAFCはこれに同意せず、その理由として、Teva社が主張する事実関係は、特許発明の自明性の推定が適用される前提(当業者の最適化への動機や日常的な実験からの期待など)を構成しないことを強調しました。CAFCは、Janssen社が1回目の投入用量を高くし、その後の2回目の投入用量を低くするという具体的な選択は、明らかに推定の範囲に当てはまらないと指摘しました。
(2)先行技術文献に基づく自明性について
自明性分析においてCAFCは、3つの主要な先行技術文献が投薬計画を開示していないと認定しました。
Teva社は、上記3つの先行技術文献以外の2つの先行文献を引用して、それらが、治療効果がより迅速に達成されるように、より大きな初期投入用量を使用すること、および、患者体内のパルミチン酸パリペリドンの過剰な蓄積を避けるために2回目の投入用量を減らして投与することを教示していると主張しました。それに対して地裁は、これらの先行文献の開示自体およびJanssen社の専門家の証言に基づく裏付けにより、これらの先行文献が、長時間作用型注射剤を使用して患者に薬剤投与することを当事者に示唆しないものと認定し、CAFCはそのような地裁の認定を支持しました。その結果CAFCは、引用された先行文献は全体としてTeva社の主張を裏付けるものではないと認定しました。
(3)安全性と効能に関する地裁の考慮について
Teva社はさらに、地裁が、クレームに記載されていない要素である安全性と効能を不適切に考慮し、複数回投与する投薬計画が当業者の意欲をそぐ複雑さを増すと認定した点で誤りがあると主張しました。この主張についてCAFCは、安全で効果的な投薬計画の開発に対する動機付けに関する地裁の判断は適切であるとの理由で却下し、先行技術には複数回投与アプローチに関連する安全性または有効性に関するデータが欠けていると正しく認定したとして、地裁の判断を支持しました。
4.実務上の留意点
本件判決の判旨から、米国における特許実務の遂行上、以下のような点に留意すべきことが読み取れます。
(1)クレームと先行技術の数値範囲が重複する場合の自明性の推定
先行技術に記載の数値範囲がクレームの範囲と重複する場合、一応の自明性が推定され得るものの、単に数値範囲が重なっているという事実だけでは必ずしも自明性が推定されるわけではなく、自明とされるためには、当業者がクレームされた発明に到達することへの動機付けや成功の合理的期待等の合理的理由の立証が必要です。
(2)二次的考慮要素の提示の有効性
CAFCが、Teva社の自明性の主張を「動機付けや成功の合理的期待を立証していない」として却下した地裁の認定を支持し、非自明性の成立のための「動機付けの欠如や成功の合理的期待の欠如」の必要性を肯定しました。このことから、発明と先行技術との間に数値範囲等の重複があっても、動機付けの欠如や成功の合理的期待の欠如、あるいは予想外の効果等の二次的考慮要素を示すことができれば、非自明性が認められる可能性があることが明確になったと言えます。予想外の効果等を示すために、特に医療分野の発明については、臨床データや実験結果を提示することが有効である場合があります。
また、動機付けや成功の合理的期待の有無の判断に際しては、動機付けや成功の合理的期待が先行技術の記載から明示的に読み取れるかどうかだけではなく、当業者の通常の創造性を考慮して判断する必要があります[viii]。
(3)専門的用語等の定義の明確化
本件判決の対象である’906特許のクレームにおいて、「投入用量(loading dose)」および「維持用量(maintenance dose)」という、投与される薬剤の量を表す技術用語が用いられ、その量の特定された数値範囲についての先行技術との対比による非自明性評価が争点の一つとなっています。このような場合、技術用語自体およびその量を表す単位について、異なる解釈の余地がないように、審査や訴訟における不確実性を回避するために、明細書で明確に定義付けておくことが望まれます。
(4)用途限定や対象者限定の問題点
本件判決の対象である’906特許のクレーム1の冒頭の前提部分に記載の病名や治療対象者の限定は、非自明性主張の根拠には必ずしもなっておらず、場合によっては保護範囲が不当に狭く解釈される恐れもあることから、クレームの前提部分をどう記載するかについては慎重な検討が望まれます。
[i] 患者のコンプライアンス:医療関係者の指示や治療方針に従って、患者が適切に服薬したり、治療に沿った行動をとったりすること。
[ii] 維持注射(maintenance injection)とは、薬物治療において、最初の投入用量(loading dosed)で血中濃度を治療に有効な濃度まで一気に上げた後、その有効濃度を一定に維持するために繰り返し所定の用量の薬剤を投与することを指します。
[iii] 投薬計画(dosing regimen)とは、薬物療法を行なう上で、薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のことをいいます。
[iv] 「mg-eq(mg当量)」について:投与されるパルミチン酸パリペリドンの量は、パルミチン酸部分が除かれた、薬効成分としてのパリペリドンの量として表され、たとえばパリペリドン100mgが含まれるパルミチン酸パリペリドン156mgがパルミチン酸パリペリドン100mg-eqに相当します。(’906特許に対応する日本特許第5825786号の段落[0040],[0059]参照)
[v] Hatch-Waxman法は、ジェネリック医薬品の承認を簡略化して供給を促進することと、先発医薬品の特許期間を延長して研究開発のインセンティブを保護すること両立させることを目的として、1984年に米国で制定された法律です。この法律により、ジェネリック医薬品メーカーが、安全で有効な先発品のデータを利用して、高額な臨床試験なしに申請できるようにした、ジェネリック医薬品の簡易承認制度(ANDA)が創設されました。
Hatch-Waxman法については、弊所HPにおいて配信した以下のURLの記事をご参照下さい。
https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/14151/
https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/13812/
[vi] プラシーボ(placebo)効果とは、薬理成分を含まない物質(偽薬、プラセボ)を服用したにもかかわらず、症状の改善や体調の変化がみられる心理現象です。
[vii] デポ製剤は、持効性注射剤(LAI:Long Acting injection)とも呼ばれ、体内で薬の成分が徐々に放出され、1回の注射で数日から数ヶ月にわたって効果が持続する注射剤のことをいいます。
[viii] KSR最高裁判決は、自明性判断に際して、先行技術文献の明示的開示だけではなく、当業者の通常の創造力を考慮すべきであると判示しています。KSR最高裁判決については、弊所HPの国・地域別IP情報において2024年4月15日付で「USPTO、自明性判断に関するガイダンスを発表」と題して配信した記事(URL: https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/11275/)をご参照下さい。
[情報元]
1.IP UPDATE (McDermott) “Motivation, expectation of success negate obviousness presumption in overlapping range case” July 17, 2025
2.Janssen Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Case No. 25-1228 (Fed. Cir. July 8, 2025)(本件CAFC判決原文)
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1228.OPINION.7-8-2025_2541042.pdf
[担当]深見特許事務所 野田 久登