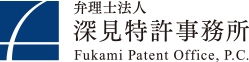明細書を補正クレームに適合させる必要があるか否かに関する質問をEPO拡大審判部に付託したEPO審判部の中間審決
欧州特許庁(EPO)では、欧州特許出願または欧州特許の明細書を、補正されたクレームに適合させる必要があるかどうかについて、この数年、相反する審決例が積み重ねられてきました。異議部の決定に対する審判事件(以下、「異議-審判事件」)T 697/22の審理を担当する技術審判部3.3.02はこの度、明細書を補正クレームに適合させる必要性についての質問事項をEPOの拡大審判部(the Enlarged Board of Appeal:EBoA)に付託する中間決定を発行しました。
Case Number: T 0697/22 – 3.3.02 “INTERLOCUTORY DECISION of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 29 July 2025”
1.背景事情
EPOの審査ガイドラインが改訂された2021年頃から、補正されたクレームに明細書を適合させる要求が、出願人および実務家にとってより厳格になり、そしてより大きな負担になっているように見受けられます[i]。この方針は以前から疑問視されてきましたが、2022年の審決T 1989/18[ii]を契機に議論が活発になってきました。以下にこの問題の議論の経緯について説明いたします。
(1)審決T 1989/18の決定内容とその後の審決
この審決においてEPOの審判部は、明細書を補正クレームに適合させることを要求しそして適合させなかった場合に特許出願を拒絶することについて、欧州特許条約(EPC)に何ら法的根拠を見出せないと認定しました。このT 1989/18の後続の他の審判事件においては、相反する審決、すなわちT 1989/18の認定を支持する審決と、明細書を補正されたクレームに適合させるという従来の確立された実務を支持する審決とが出されました。
(2)本稿の対象となる審判事件の経緯
本稿で取り上げるEBoAへの付託が行われた審判事件T 697/22は異議-審判事件であり、その前段階の異議申立手続において特許権者は、異議申立に対処するためにクレームを補正し、その補正クレームについて異議部は特許性を有すると認めました。しかしながら、特許権者が、EPC第84条[iii]に準拠して補正されたクレームとの潜在的な不一致を除去することを目的として明細書の補正された部分を提出したのは、異議申立人が異議部の決定に不服を唱えて審判部に請求した異議-審判事件の審理が始まってからでした。審判部は、遅れて提出された書面は審判事件の補正を構成すると判断し、審判部手続規則(Rules of Procedure of the Board of Appeals:RPBA)13(1)および(2)[iv]に照らしてこれを受理しませんでした。したがって、特許権者は、特許可能なクレームを有する一方で補正クレームに十分に適合した明細書を有していないというジレンマに直面することになりました。明細書が補正クレームに十分に適合されていない場合は通常、特許は補正された形で維持することはできません。
(3)EBoAへの付託に至る経緯
上記のジレンマは審判部に重大な疑問を生じさせました。すなわち、EPCの要件を遵守するために不一致を解消するように明細書を補正後のクレームに適合させる必要があるのかという疑問です。もしも必要でなければ、審判事件T 697/22における特許権者はこれ以上適合させた明細書を提出する必要はなく、特許は補正された形で維持されるでしょう。そうでなければ、特許権者は、明細書の補正を強いられながらも手続法によりそれが禁じられているという、一見逃れられない窮地に陥ることになります。
審判部は、明細書の適合という争点に関する判例法の検索を開始し、1983年4月から2025年2月までの115件の関係する審決を検索し、判例法の2つの異なる方向性を確認しました。第1の方向性は、過去の多くの審決で言及されたように明細書を補正されたクレームに適合させるという従来の確立された実務を支持するものであり、第2の方向性は最近のいくつかの審決におけるもので明らかに第1の方向性とは相反し、クレーム補正の結果、補正クレームと明細書との間に不一致が生じても特許出願を拒絶する法的根拠は存在しない、というものでした。
本件において審判部は、法律の統一的な適用を担保する目的で、EBoAへの付託を自ら動議として決定しました。この付託には、番号G 1/25が割り当てられました。
2.付託された質問事項
G 1/25において、審判部は以下の3つの質問をEBoAに付託しました。
(1)第1の質問事項
欧州特許のクレームが異議申立手続中または異議-審判手続中に補正され、その補正によって補正後のクレームと特許明細書との間に不一致が生じた場合、EPCの要件を遵守するために、不一致を解消するように明細書を補正クレームに適合させる必要があるのか?(2)第2の質問事項
第1の質問事項への回答が肯定的である場合、EPCのどの要件がそのような適合を必要とさせているのか?
(3)第3の質問事項
欧州特許出願のクレームが審査手続中または審査部の査定に対する審判手続中に補正され、その補正によって補正後のクレームと特許出願の明細書との間に不一致が生じた場合、明細書を補正クレームに適合させる必要があるのか、また回答が肯定的である場合、EPCのどの要件がそのような適合を必要とさせているのか、という質問については、異議申立手続中または異議-審判手続中の補正に関する上記の質問事項1および2に対する回答とは異なった回答になるのか?
3.質問事項に関する補足説明
(1)第1の質問事項に関する補足説明
第1の質問事項は、そもそも明細書を補正する必要があるかどうかという根本的な問題に向けられています。これには、クレームが補正されたこと、および補正によって明細書との不一致が生じること、というきっかけとなる条件が含まれます。正確にはどのような不一致が生じる可能性があるかは定義されていません。さらに、第1の質問事項は、当然のことながら、異議申立または異議-審判手続の文脈で提起されています。さらに、明細書を補正する必要があるかどうかは、「EPCに規定された要件」を遵守するかどうかの問題であり、すなわちEPCまたはEPC規則のどの条項を遵守するのかという問題になります。このような条文との法的整合性の問題は第2の質問事項で扱われます。
(2)第2の質問事項に関する補足説明
第2の質問事項は、EBoAに対し、明細書の適合を求める法的根拠を徹底的に検討し、この点を明確に述べるよう促す意図で提起されたように思われます。付託を行った審判部は、明細書の補正を求める法的根拠に関する判例法のばらつきを根拠として、この質問を正当化しています。実際、明細書の適応の必要性に異議を唱えたいくつかの審判部は、明確な法的根拠がないと主張しています。一方、反対の見解を支持するいくつかの審判部は、しばしばEPC第84条に由来するサポートおよび整合性に依拠しています。この質問に対するいかなる回答も、明確性と法的確実性をもたらすでしょう。
(3)第3の質問事項に関する補足説明
第3の質問事項は、第1および第2の質問事項を審査手続における明細書の補正にまで拡大しているため、実務上の関心が高いものです。審判部は、これをEPOの全部門の実務に影響を与える基本的な法律問題とみなしています。実際、EBoAが適合性に関する明細書の補正の必要性を否定すれば、EPOの特許審査の日常業務が根本的に変わる可能性があります。
4.今後の展望
(1)付託に対する決定の時期的予想
EBoAは今後、この付託を検討する予定です。EBoAはEPO長官に意見を求め、第三者にアミカス・ブリーフ[v]を提出するよう求める可能性があります。口頭審理が行われる可能性が高く、決定は口頭審理の終了時か、数ヶ月後に言い渡される可能性があります。これにどれくらいの時間がかかるかを予測することは困難です。最近決定された付託案件から判断すると、G 1/25におけるEBoAの決定は、2026年夏頃またはそれ以降に発せられると予想されます。
(2)手続進行中の案件の停止の可能性
付託案件および進行中の手続に関して、EPO審査ガイドライン[vi]は、次のように規定しています。
**********
EBoAへの付託が係属中であり、審査または異議申立手続の結果がEBoAに付託された質問事項への回答に完全に依存している場合、審査部または異議部は、自らの判断または当事者(複数可)の要請により、手続を停止することができる。
**********
したがって、原則として、本付託案件は、関連する審査および異議申立手続の停止を要請する機会を提供します。理論的には、これにより、補正されたクレームと明細書との間の不一致を解消する必要があるすべてのEPO手続が停止される可能性があります。しかし、EPOは最近、法的確実性を確保するため、審査および異議申立手続きを継続し、EPOの審査ガイドラインに述べられている実務、すなわち補正されたクレームに明細書の記載を適合させることを義務付ける実務方針を適用する、と公式ウェブサイトにおいて既に発表しています[vii]。
(3)関連するEBoAの審決G 1/24
注目すべきことに、別件のEBoAへの付託(G 1/24)に対してEBoAよって最近出された決定[viii]は、クレームの解釈において明細書をより重視することを明らかにしました。本件付託(G 1/25)に対するEBoAの回答はまさに、そもそも明細書を「形成」することに関するものであり、明細書はその後、クレームの解釈の重要な情報源となります。本件において付託を行った審判部は、その中間決定(情報源②)のセクション21.4の第3段落において、「G 1/24を受けて、補正されたクレームと明細書との間に不一致がある場合、出願が認められるか、または特許が維持されるか、という問題は、さらに重要性を増している。」とのべ、その疑問はG 1/24に鑑み根本的な法的疑問であると適切に説明しています。
結論として、判例法におけるばらつきの増大とそれに伴う法的不確実性を考慮すると、本件のEBoAへの付託は望ましいことであります。もしもEBoAが明細書の補正に関するEPOの現在の厳格な方針を緩和すれば、出願人と実務家の負担は軽減されるでしょう。そのような場合には、明細書に残る、補正クレームとの明白な不一致は、別件の付託(G 1/24)に対する回答に従って明細書を重視してクレームを解釈する際には、適切に対処する必要があります。
[i] 2021年のEPO審査ガイドラインの改訂については、2021年4月6日付けの弊所HPの記事「EPO審査ガイドラインの改訂」の「II.『クレームとの対応に関する明細書の記載要件の厳格化』(Part F-IV.4.3(iii))に関する改訂内容について」をご参照ください。(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/6303/)
[ii] T 1989/18 (Adaptation of the description/HOFFMANN-LA ROCHE) 16-12-2021
(https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t181989eu1)
[iii] EPC第84条は以下のように規定しています(括弧内は日本国特許庁による翻訳)
“Article 84 Claims
The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.“
(第84条 クレーム
クレームには,保護が求められている事項を明示する。クレームは,明確かつ簡潔に記載し,明細書により裏付けがされているものとする。)
[iv] 本件の中間決定原文(情報元②)のセクション9.4にはこれらの規則について以下のように説明されています。
“Under Article 13(1) RPBA, any amendment to a party’s appeal case after it has filed its grounds of appeal or reply is subject to the party’s justification for its amendment and may be admitted only at the discretion of the board. The board will exercise its discretion in view of, inter alia, the current state of the proceedings and whether the amendment is detrimental to procedural economy.
Under Article 13(2) RPBA, any amendment to a party’s appeal case made after notification of a summons to oral proceedings must, as a rule, not be taken into account unless there are exceptional circumstances justified with cogent reasons by the party concerned.”
[v] アミカス・ブリーフとは、一般的に訴訟等の当事者ではない第三者が提出する情報や意見を指します。
[vi] 審査ガイドライン:Part E-Chapter VII-Section 3 “Stay of proceedings when a referral to the Enlarged Board of Appeal is pending”(https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/e_vii_3.html)
[vii] “Referral G1/25 on adaptation of the description”
(https://www.epo.org/en/news-events/news/referral-g125-adaptation-description)
[viii] 弊所ホームページの「国・地域別IP情報」の2025年11月11日付け配信記事「付託G1/24に関する拡大審判部の決定」(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/14801/)において詳細に解説しておりますのでご参照ください。
[情報元]
1.Hoffmann Eitle Quarterly September 2025
“Amendment of the Description at the EPO: The Time Has Come! – Referral G 1/25”
(https://www.hoffmanneitle.com/it/2025_q3_newsletter_server.htm)
2.Case Number: T 0697/22 – 3.3.02
“INTERLOCUTORY DECISION of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 29 July 2025”(EPO審判部の中間決定原文)
(https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t220697ex1.pdf)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊